
あなたは「自分は大丈夫」そう思っていませんか?
実は、自覚症状が出にくいまま進行し、放っておくと、高血圧や糖尿病、心筋梗塞、脳卒中など、命に関わる病気を引き起こすリスクが高まります。
その病気とは「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」。
特に肥満体型の方は要注意です。 首回りに脂肪がつくと、睡眠中に呼吸が止まってしまうことがあります。
「あれ?もしかして私も?」 そう思った方は、まずは生活習慣を見直してみましょう。
この記事では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の具体的な対策について解説し、原因や予防法にも触れていきます。 ご自身の状況と比較しながら、読み進めてみてください。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策には生活習慣の改善をすること!
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたり、心配な症状がある方は、まずできることから取り組んでみましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたり、心配な症状がある方は、まずできることから取り組んでみましょう。
日々の生活習慣を少し見直すだけで、症状が改善する可能性があります。
食事制限・減量
肥満は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の大きなリスク要因の一つです。睡眠時無呼吸症候群の患者さんを診察していると、多くの方が肥満傾向にあることに気づきます。 太っている方の気道は、まるで風船がしぼんだように狭くなっていることが多く、睡眠中に呼吸が止まりやすい状態です。
首回りに脂肪がつくと、さらに気道が狭くなり、睡眠中に呼吸が止まりやすくなります。 食事の内容を見直し、適正体重を目指しましょう。
目標体重を達成するために、患者さん一人ひとりのライフスタイルに合わせた無理のない食事療法の提案をしています。 例えば、
- 塩辛いものや甘いもの、炭水化物を摂り過ぎていないか?
- 毎食、野菜を食べているか?
- 魚より肉を食べることが多くないか?
- 揚げ物やバター、生クリーム、チーズを使った料理を食べることが多くないか?
などをチェックしてみましょう。
また、サラダやスープなど低カロリーのものを先に食べ、高カロリーのものを後回しにするのも効果的です。
食物繊維の多い食品を最初に食べることで、血糖値の急上昇を抑え、食べ過ぎを防ぐ効果も期待できます。
飲酒の制限
寝る前のアルコールは、気道の筋肉をリラックスさせてしまい、気道が狭くなる原因になります。 これは、飲酒によって気道を広げる筋肉が緩み、舌根沈下を起こしやすくなるためです。 特に就寝前の飲酒は控え、適量を守るようにしましょう。 具体的には、ビールであれば中瓶1本、日本酒であれば1合程度を目安にすることをお勧めしています。
睡眠薬・精神安定剤などの制限
睡眠薬や精神安定剤も、アルコールと同様に気道の筋肉を弛緩させる作用があるため、睡眠時無呼吸症候群の症状を悪化させる可能性があります。
これらの薬は、脳の活動を鎮静化させることでリラックス効果をもたらしますが、その一方で気道の筋肉も緩めてしまうことがあります。
これらの薬を服用している場合は、医師に相談の上、使用を控えるか、他の薬への変更を検討してみましょう。 自己判断で服用を中止することは大変危険ですので、必ず医師の指示に従ってください。
禁煙
タバコは、気道に炎症を起こし、気道を狭くするため、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めます。
タバコの煙に含まれる有害物質は、気道の粘膜を刺激し、炎症や腫れを引き起こします。
その結果、気道が狭くなり、呼吸が苦しくなってしまうのです。 禁煙することで、睡眠時無呼吸症候群だけでなく、様々な病気のリスクを減らすことができます。
禁煙は睡眠時無呼吸症候群の予防と改善だけでなく、動脈硬化の予防、肺がんのリスク低下など、多くの健康効果をもたらします。
禁煙外来などを活用し、医師や薬剤師のサポートを受けながら禁煙に挑戦してみるのも良いでしょう。
寝方(寝る姿勢)の改善
仰向けで寝ると、舌がのどの奥に落ち込みやすく、気道を狭くしてしまうため、睡眠時無呼吸症候群の症状が悪化しやすくなります。
仰向けで寝ることで重力によって舌根が気道に沈下しやすくなるためです。 気道の断面積が狭くなることで、空気の通りが悪くなり、いびきや無呼吸を引き起こしやすくなります。
横向きで寝ることで、気道が確保されやすくなるため、睡眠時無呼吸症候群の予防・改善に効果が期待できます。 横向きで寝る場合は、重力の影響を受けにくく、舌根が気道に沈下しにくいためです。
横向きで寝ることに慣れていない場合は、抱き枕を使ったり、体の後ろにクッションを置いたりすることで、楽な姿勢を保つことができます。
運動
適度な運動は、体重管理だけでなく、ストレス軽減や睡眠の質向上にも効果があり、睡眠時無呼吸症候群の予防・改善にも役立ちます。
運動不足は肥満の一因となり、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めるだけでなく、自律神経のバランスを崩し、睡眠の質を低下させることにもつながります。
激しい運動である必要はありません。
毎日、エレベーターやエスカレーターではなく階段を使う、一駅手前で降りて歩くなど、できることから始めてみましょう。
軽い運動でも、継続することで心肺機能が高まり、基礎代謝がアップし、太りにくい体作りに繋がります。
口呼吸から鼻呼吸へ
口呼吸は、気道を乾燥させ、炎症を起こしやすくするため、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めます。
口呼吸は、鼻呼吸に比べて、空気中のウイルスや細菌を直接体内に取り込みやすく、感染症のリスクを高める可能性もあります。
また、口呼吸を続けることで、顔の筋肉のバランスが崩れ、口元が出てきたり、顔色が悪くなったりするなど、美容面への影響も懸念されます。
鼻呼吸を心がけることで、気道の乾燥を防ぎ、睡眠時無呼吸症候群の予防・改善に繋げることができます。
鼻呼吸には、空気を加湿・加温する、ウイルスや細菌をフィルターする、などの役割があります。 鼻づまりの原因となっているアレルギー性鼻炎などの治療を行うことも有効です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策グッズ
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたら、生活習慣の改善と並行して、医療機器やグッズを取り入れてみましょう。 ここでは、代表的な対策グッズを3つご紹介します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたら、生活習慣の改善と並行して、医療機器やグッズを取り入れてみましょう。 ここでは、代表的な対策グッズを3つご紹介します。
枕
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の方におすすめの枕は、横向き寝になったときに、頭と体の軸がまっすぐになる高さが重要です。
低すぎると気道が狭くなってしまいやすいためです。 低すぎる枕は、まるで頭を地面につけたまま横向きになっているようなもので、気道が圧迫されやすくなります。
一方、高すぎる枕は、首に負担がかかり、筋肉が緊張して気道を狭くしてしまう可能性があります。
枕の素材は、低反発素材よりも、頭が沈み込みすぎない高反発素材がおすすめです。 低反発素材は、頭や首にフィットして心地よいと感じるかもしれませんが、睡眠時無呼吸症候群の方にとっては、気道を圧迫するリスクがあります。
高反発素材は、適度な反発力で頭と首を支え、気道を確保しやすいため、睡眠時無呼吸症候群の方に向いています。
枕を選ぶ際には、実際に寝転んでみて、呼吸のしやすさを確認することが大切です。
お店で試す際には、恥ずかしがらずに、横向き寝になってみて、呼吸が楽にできるかどうか、首や肩に負担がかからないかどうかを確認しましょう。
マウスピース
マウスピースは、就寝時に装着することで、下あごを少し前に出すことで気道を確保し、無呼吸状態を予防する効果があります。
歯に装着することで、顎の位置を少しずらし、気道の空間を人工的に広げるイメージです。 マウスピースには、歯科医院で歯型を取って作製するオーダーメイドのものと、ドラッグストアなどで購入できる既製品のものがあります。
オーダーメイドのものは、自分の歯型にぴったりとフィットするため、装着感が良く、効果も高い傾向がありますが、費用は比較的高額です。
一方、既製品のものは、安価で手軽に購入できますが、フィット感が悪く、効果が低い場合があります。
費用と効果のバランス、そしてご自身の口腔内の状態などを考慮して、どちらのタイプが適しているか、医師と相談してみましょう。
マウスピースは、毎日使用し、定期的に交換する必要があるため、費用や手間を考慮して選ぶようにしましょう。
毎日歯磨きをするように、マウスピースも清潔に保つことが大切です。
いびき防止グッズ(鼻用テープやピン)
いびき防止グッズには、鼻に貼るテープや、鼻腔を広げるピンなど、様々な種類があります。
これらのグッズは、比較的安価で、手軽に使用できるというメリットがありますが、効果には個人差があります。
鼻に貼るテープは、鼻翼(鼻の穴の外側の部分)を軽く持ち上げることで、鼻腔を広げ、鼻呼吸をしやすくする効果があります。
鼻腔を広げるピンは、鼻の穴に挿入して、鼻腔を広げる効果があります。
しかし、テープやピンを長時間使用すると、皮膚がかぶれたり、痛みが出たりすることがあるため注意が必要です。
また、鼻づまりの原因がアレルギー性鼻炎などの場合は、これらのグッズだけでは十分な効果が得られないこともあります。
いびき防止グッズは、あくまで一時的な対策であり、根本的な治療にはなりません。
いびきがひどい場合は、医療機関を受診して、適切な治療を受けるようにしましょう。
医師の診断のもと、適切な治療法を選択することが大切です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治し方
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されると、不安な気持ちになる方もいるかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されると、不安な気持ちになる方もいるかもしれません。
しかし、睡眠時無呼吸症候群は適切な治療と生活習慣の改善によって、症状をコントロールできる病気です。
治療法は、軽症から重症まで、患者さん一人ひとりの状態に合わせて選択されます。 まず、睡眠時無呼吸症候群の治療で最も重要な柱となるのが「生活習慣の改善」です。その中でも「肥満」は睡眠時無呼吸症候群に深く関わっており、体重増加によって気道が狭くなることで、無呼吸状態になりやすくなります。 例えるなら、空気の通り道である気道が、脂肪によって圧迫されて狭くなってしまうイメージです。
実際に、私の患者さんの中にも、10kgの減量に成功しただけで、睡眠時無呼吸症候群の症状が劇的に改善した方がいらっしゃいます。 減量以外にも、飲酒や喫煙、睡眠薬の使用なども、睡眠時無呼吸症候群の症状を悪化させる可能性があります。飲酒は、気道の筋肉を弛緩させてしまい、気道が狭くなる原因となります。
特に寝る直前の飲酒は、睡眠中の無呼吸のリスクを高めるため、控えるようにしましょう。
喫煙も、気道に炎症を起こし、気道を狭くするため、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高める要因となります。禁煙は睡眠時無呼吸症候群の予防と改善だけでなく、動脈硬化の予防や肺がんのリスク低下など、様々な健康効果をもたらします。
睡眠薬や精神安定剤も、気道の筋肉を弛緩させる作用があるため注意が必要です。これらの薬を服用している場合は、自己判断で中断するのではなく、必ず医師に相談するようにしてください。
生活習慣の改善と合わせて、横向きで寝ることも効果的です。仰向けで寝ると、舌が喉の奥に落ち込みやすく、気道を狭くしてしまうため、睡眠時無呼吸症候群の症状が悪化しやすくなります。
横向きで寝る場合は、重力の影響を受けにくく、舌が気道に沈下しにくいため、呼吸が楽になります。 横向きで寝ることに慣れていない方は、抱き枕を使ったり、体の後ろにクッションを置いたりすることで、楽な姿勢を保つことができます。
これらの生活習慣の改善は、睡眠時無呼吸症候群の症状を和らげるだけでなく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防にもつながります。
ご自身の健康のためにも、できることから少しずつ改善していくように心がけましょう。
睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合はオンライン診療へ
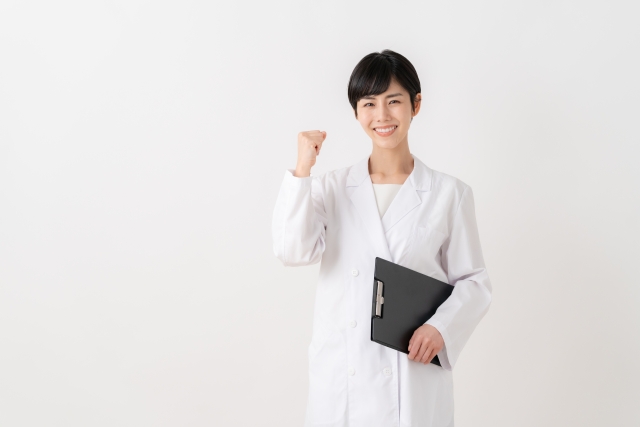 「もしかして、睡眠時無呼吸症候群(SAS)かもしれない…」
「もしかして、睡眠時無呼吸症候群(SAS)かもしれない…」
と感じながらも、忙しい毎日の中で、なかなか医療機関を受診できない方もいるかもしれません。
「毎日ぐっすり眠れている自信がない」「日中、強烈な眠気に襲われることがある」「パートナーにいびきや呼吸が止まっていることを指摘された」
このような経験はありませんか?
これらの症状は、睡眠時無呼吸症候群のサインかもしれません。 特に、太り気味の方や首が短く太い方は、気道が狭くなりやすく、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高いと言われています。
しかし、多くの方が「自分は大丈夫だろう」と軽く考えてしまいがちです。 「ちょっと疲れているだけ」「そのうち治るだろう」と放置してしまうケースも少なくありません。
睡眠時無呼吸症候群は早期発見・早期治療が何よりも重要です。 「もしかして…」と思ったら、一人で悩まず、まずは専門医に相談してみましょう。
最近は、オンライン診療に対応している医療機関も増えています。 自宅にいながら診察を受けられるので、忙しい方でも受診しやすいというメリットがあります。
オンライン診療では、睡眠時無呼吸症候群の症状や疑いについて相談したり、検査方法や治療法について説明を受けたりすることができます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療
- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?
- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します
検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?
予防
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介
合併症
症状
原因
傾向
疑い

