
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療法として知られるCPAP(シーパップ)ですが、「人工呼吸器(生命維持装置)と同じものなの?」「安全なのだろうか?」と不安に思う方も多いでしょう。
本記事では、専門医がCPAPと人工呼吸器の違いを分かりやすく解説し、CPAP治療の安全性や、逆に治療しない場合のリスクについてエビデンスに基づき徹底解説します。
さらに、CPAPに関するよくある疑問にもQ&A形式でお答えします。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
CPAPと人工呼吸器(生命維持装置)の違い

CPAPと一般的な「人工呼吸器」はともに呼吸をサポートする医療機器ですが、その目的や役割は大きく異なります[3]。
簡単に言えば、CPAPは睡眠中に空気の通り道(気道)が塞がらないように支えるための装置で、主に睡眠時無呼吸症候群(SAS)の患者さんに対して夜間に使用します。
一方、人工呼吸器(生命維持装置)は患者さん自身の呼吸が極めて弱いか止まってしまっている場合に、呼吸そのものを機械が代行・補助して生命を維持するために使われる装置です[3]。
人工呼吸器は重篤な呼吸不全に陥った患者や手術中の麻酔下などで用いられ、気管挿管や気管切開を伴うこともあります。
具体的な違いを挙げると、CPAPは鼻や口にマスクを装着し常に一定の陽圧(空気圧)を気道に送り込みます。これにより睡眠中も喉や気道が開いた状態に保たれ、無呼吸や低呼吸を防ぐ仕組みです。
一方で人工呼吸器は、患者さんの肺に酸素を送り込み二酸化炭素を排出する呼吸動作自体を助ける/代行する機能を持ち、患者さんの呼吸回数や吸入量を機械がコントロールできます[3]。
つまり、CPAPは患者自身の自発呼吸が前提で「空気の通り道を支える」装置であり、人工呼吸器は自発呼吸が困難な人の「呼吸そのものを維持する」装置なのです。
実際、睡眠時無呼吸症候群の治療に使われる家庭用CPAP装置は、集中治療室などで使われる高度な生命維持装置としての人工呼吸器とは明確に区別されます[3]。
CPAPはマスクを介して空気圧をかける非侵襲的な療法であり、気管挿管などの侵襲を伴わない点も人工呼吸器との大きな違いです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
CPAP治療の安全性と、治療をしないことの本当のリスク
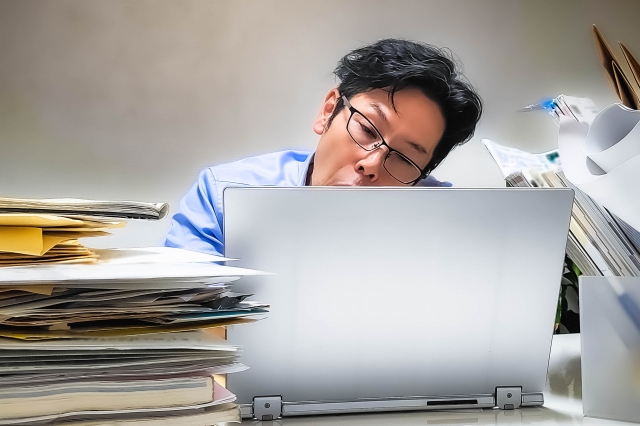
CPAPは世界中で行われている安全な治療法です
CPAP療法は閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)に対する第一選択の標準治療であり、世界中で広く行われています[2]。
日本でも1998年に健康保険適用となって以来、多くの患者さんがCPAPによって症状の改善を実感しています[2]。
CPAP装置は卓上に置ける小型の機械で、基本的には空気を送り出すポンプとホース、マスクで構成されており、薬剤を使わず空気圧だけで治療できるのが特徴です。
そのため副作用は比較的少なく、適切に使用すれば安全性の高い治療と言えます。実際にCPAP治療によって睡眠中の低酸素状態が解消し、日中の眠気や倦怠感の改善、高血圧の是正など多くの有用性が報告されています。
重症のSAS患者さんを対象とした研究でも、CPAPを行った群は行わなかった群に比べて明らかに長生きできたとの結果が示されるなど、CPAP療法の有効性・安全性は数多くの研究で証明されています[2]。
現在では中等度~重度のSAS患者さんにはCPAPが世界的に標準治療として推奨されており、毎晩世界中の患者さんがCPAP装置を使用して安眠を取り戻しています。
マスク装着による違和感や、鼻・喉の乾燥など多少の副作用はありますが、こうした問題も加湿器の併用やマスクの工夫で改善できます。
総じて、CPAPは適切な指導のもとで使用すれば長期にわたり安全に継続できる治療法です。
本当に怖いのは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を放置することです
CPAPそのもののリスクよりも、治療せずにSASを放置することの方が遥かに危険です。
睡眠時無呼吸症候群は単なる「いびき」や「寝不足」の問題ではなく、放置すれば全身に様々な悪影響を及ぼします。
例えば、睡眠中の無呼吸により慢性的な低酸素状態と睡眠の分断が起こると、交感神経が過剰に刺激されて高血圧、心拍数の増加、不整脈など心血管系への負担が生じます。
その結果、心筋梗塞や脳卒中、心不全など致命的な合併症のリスクが高まります。また、夜間の低酸素は糖尿病やメタボリックシンドロームの悪化要因ともなり得ます。
さらに、睡眠の質の極度の低下から日中の強い眠気が生じ、居眠り運転による交通事故など重大な事故の危険性も指摘されています。
ある18年間の追跡研究では、重症の睡眠時無呼吸症候群の人は、症状がない人に比べて全死亡リスクがおよそ3倍にも達し、適切に治療しなかった場合はそのリスクがさらに高まったことが示されています[1]。
特にCPAP等による治療を受けなかった重症患者では、心血管死亡リスクが治療例の約2倍から5倍近くに跳ね上がったとの報告もあり、CPAP治療が命を守る可能性を示唆しています[1]。
このように、本当に怖いのはCPAP装置ではなく、睡眠時無呼吸症候群そのものを放置することなのです。
適切な治療を受けず無呼吸状態が続けば、知らず知らずのうちに健康寿命を縮め、突然死のリスクすら高めかねません。
SASは早期発見・早期治療が何より重要な疾患であり、少しでも疑わしい症状があれば放置せず専門医に相談することが大切です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
CPAPと「人工呼吸器」に関するよくある質問(Q&A)

CPAPを使うと、医療費控除の対象になりますか?
A. はい、CPAP治療にかかった費用は条件を満たせば医療費控除の対象になります。
CPAP療法は医師の管理下で行う継続的な治療であり、健康保険適用であれば毎月の自己負担金(装置のレンタル料や診察費等)は医療上必要な費用として確定申告時に医療費控除の対象となります[4]。
年間の医療費自己負担額が一定額(通常10万円)を超える場合、確定申告を行うことで所得税の還付や住民税の軽減が受けられます。
ただし注意点として、CPAP装置を医師の関与なしに全額自己負担で購入した場合(日本では一般にCPAPは医師の処方のもとレンタルする形ですが、何らかの理由で自費購入したケース)には、その購入費用自体は医療費控除の対象とならないのが原則です[4]。
これは眼鏡や補聴器と同様、「治療の対価」とみなされないためですが、通常の保険診療でCPAPを利用する限り心配いりません。領収書を保管のうえ、確定申告時に忘れずに申請しましょう。
CPAPの使用で、身体障害者手帳の対象になりますか?
A. 一般的にはCPAPを使っていること自体で身体障害者手帳の交付対象になることはほとんどありません。
身体障害者手帳は視覚や聴覚、呼吸機能などに永続的な障害がある場合に交付されますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)単独では日常生活における身体機能の著しい制限と見なされないことが多いためです[5]。
基本的には、SASによって重度の呼吸不全や心不全など他の合併症を伴い、日常生活に著しい支障が出ている場合に限り、呼吸器機能障害として障害者手帳の等級が認定される可能性があります[5]。
例えばSASが原因で覚醒時にも低酸素血症が生じるほどの深刻な呼吸障害がある場合などが該当します。その際は医師の診断書が必要で、各自治体の審査で認定されれば手帳取得となります。
ただ、CPAPで無呼吸がコントロールされ日常生活が送れている状態であれば、手帳の対象にはならないのが通常です。障害年金についても同様に、SASだけで認定されるケースは稀で、他の重篤な合併症を伴う場合に検討されることになります。
CPAP治療を一度始めたら、一生やめられないのでしょうか?
A. 現状では、多くの患者さんにとってCPAP治療は長期継続が前提となります。CPAPは根本的に睡眠時無呼吸の原因を取り除く「治療薬」ではなく、睡眠中だけ症状を抑える「対症療法的な装置」です[6]。
CPAPを使用している間は無呼吸を防げますが、機械を外せば再び気道が塞がって無呼吸が起きる可能性があります。
特に肥満が原因でOSAになっている場合、体重を減らすことで症状改善が期待できますが、それでも10%の減量で無呼吸・低呼吸の回数が20%程度減るにとどまるとの報告があり、重症の方では多少体重を減らしてもCPAP無しで十分な呼吸が確保できないケースが多いのです[6]。
つまり、CPAPは高血圧における降圧薬や、視力矯正の眼鏡のように、「症状をコントロールするために使い続けるもの」と考えるのがよいでしょう。
もちろん、中等度のSASであれば歯科装置(マウスピース)や体位療法、生活習慣の改善でCPAPを使用せずに改善する例もありますし、肥満の方が大幅な減量に成功してCPAPが不要になる可能性もあります。
しかし現実には、一度CPAPが必要な程度の重症OSAと診断された方の多くは、何らかの根本治療(体重減少や外科手術など)を行わない限りCPAPをやめるのは難しいのが実情です[6]。
CPAPを中断すれば再び睡眠中の無呼吸が増えてしまうため、主治医と相談しながら無理のない範囲で上手に付き合っていくことが大切です。
ただし、「一生やめられない」と悲観する必要はありません。将来的に画期的な治療法が開発されたり、著しい体質改善が得られればCPAP卒業もあり得ますし、何よりCPAPによって得られる快適な睡眠と健康維持のメリットは計り知れません。
CPAP治療を続けることで得られる日中の爽快感や合併症予防の効果は、装置の手間を上回る価値があります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある場合はオンライン診療へ

睡眠時無呼吸症候群は適切な治療で生活の質を大きく向上させることができます。
もし「いびきがひどい」「日中の強い眠気が続く」「夜間に呼吸が止まっていると指摘された」などSASの疑いがある場合は、放置せず早めに医療機関に相談しましょう。
当院(森下駅前クリニック)では睡眠時無呼吸症候群に対するオンライン診療を実施しています。
忙しくて通院が難しい方や遠方の方でも、自宅にいながら専門医の診察を受け、必要な検査や治療の提案を受けることが可能です。
オンライン診療であれば、問診や簡易検査の結果確認、CPAP治療の導入や継続フォローまで、来院の負担を減らしてSASのケアを行えます。
「もしかして…」と思い当たる症状がある方は、ぜひ一度オンライン診療をご利用ください。早期に適切な対応を行い、質の高い睡眠と健康な生活を取り戻しましょう。
お問い合わせ・ご相談もお気軽にどうぞ。あなたの健やかな眠りを、私たちがサポートいたします。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療
- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?
- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します
検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?
予防
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介
合併症
症状
原因
傾向
疑い
参考文献
[1] Young T et al. Sleep-Disordered Breathing and Mortality: Eighteen-Year Follow-Up of the Wisconsin Sleep Cohort. Sleep. 2008;31(8):1071-1078.
[2] 日本呼吸器学会 呼吸器Q&A Q30「CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」※一般社団法人日本呼吸器学会 市民向けサイトより (閲覧日: 2025年8月9日).
[3] 岸田 雄治 「CPAPは人工呼吸器とどう違う?NPPVとの比較と医療現場での役割」神戸きしだクリニック 呼吸器内科 (2025年6月30日公開).
[4] 岸田 雄治 「CPAPの購入費用と保険適応|自費診療と医療費控除の仕組み」神戸きしだクリニック 呼吸器内科 (2025年6月6日公開).
[5] 愛媛・松山障害年金相談センター 「睡眠時無呼吸症候群で障害者手帳・障害年金を取得する方法とそのメリット」 (ウェブ記事, 2023年).
[6] 大阪回生病院 睡眠医療センター 「睡眠時無呼吸症候群(SAS)に関するQ&A」 (病院ウェブサイト, 閲覧日: 2025年8月9日).

