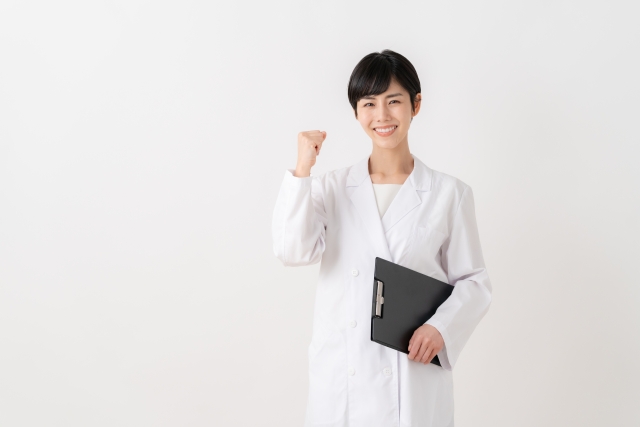睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症割合はどれくらい?

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、思われている以上に多くの方が抱える睡眠障害です。
世界的な調査によると、一般成人人口の約9-38%が睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断基準を満たすとされています[1]。
日本においては、成人の約3-7%が閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)を有すると推定されており、その多くが未診断のまま放置されています[2]。
特に注目すべきは、重症度によって分類すると、軽症(AHI 5-15)が最も多く、全体の約60-70%を占めるという点です。
中等症(AHI 15-30)は約20%、重症(AHI 30以上)は約10-15%と推定されています[3]。
日本人の特徴として、欧米人に比べて肥満度が低くても発症することが知られており、これは東アジア人に特有の顔面骨格(小さな下顎、上気道の解剖学的特徴)が関連していると考えられています[4]。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
年代別・性別の割合と特徴

性別による差異
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は男性に多い疾患として知られています。
疫学調査によれば、成人男性の約10-17%、成人女性の約3-9%が睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断基準を満たすとされています[5]。
この男女差は特に40-60歳の年齢層で顕著です。
男女差が生じる理由としては、以下のような要因が考えられています:
- ホルモンの影響:女性ホルモンが上気道の筋緊張を保ち、閉塞を防ぐ効果がある[6]
- 体脂肪分布の違い:男性は首周りや上気道周囲に脂肪がつきやすい[7]
- 上気道の解剖学的差異:男性は気道が長く、閉塞しやすい構造がある[8]
しかし、女性は閉経後に睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症率が上昇する傾向があり、50歳以上では男女差が縮まることも報告されています[9]。
関連記事
女性にも多い睡眠時無呼吸症候群(SAS)|見逃されやすい症状と治療法をわかりやすく解説
年代別の特徴
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の有病率は年齢によって大きく変動します:
- 小児期(2-8歳):約1-5%。主に扁桃肥大や腺様増殖症が原因となることが多い[10]
- 思春期〜若年成人(15-30歳):約2-3%。この年代では肥満との関連が強まる[11]
- 中年期(30-60歳):約10-17%(男性)、3-9%(女性)。最も有病率が高い年代[12]
- 高齢期(65歳以上):約20-30%。加齢に伴う筋力低下や体型変化が影響[13]
年齢が上がるにつれて睡眠時無呼吸症候群(SAS)の有病率は上昇し、特に65歳以上の高齢者では、軽症を含めると3人に1人の割合で睡眠時無呼吸症候群(SAS)が見られるという研究結果もあります[14]。
関連記事
高齢者の睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?症状・原因・治療法を徹底解説!
地域・人種による差異
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の有病率には地域差や人種差も報告されています:
- アジア人(日本人含む)は欧米人に比べてBMIが低くても発症しやすい[15]
- アフリカ系アメリカ人は白人に比べて若い年齢で発症する傾向がある[16]
- 先住民族(オーストラリア先住民、ニュージーランドマオリ族など)では有病率が特に高い[17]
関連記事
「睡眠時無呼吸症候群(SAS)はどんな人がなるの?」傾向と特徴を徹底解説
痩せてるのに睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性あり?原因・リスク・治療法を徹底解説!
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)を放置するとどうなる?

睡眠時無呼吸症候群(SAS)を放置することによる健康リスクは多岐にわたり、重症度や罹患期間に比例して深刻化します。
循環器系疾患リスクの上昇
- 高血圧:未治療の睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者の約50%が高血圧を合併しており、特に夜間の「仮面高血圧」が特徴的です[18]。重症睡眠時無呼吸症候群(SAS)では治療抵抗性高血圧のリスクが2-3倍に上昇します[19]。
- 心房細動:睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者は心房細動の発症リスクが2-4倍高く、特に60歳以上の患者で顕著です[20]。また、カテーテルアブレーション治療後の再発率も高いことが報告されています[21]。
- 冠動脈疾患:中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群(SAS)では、心筋梗塞のリスクが約2倍に上昇します[22]。無呼吸による低酸素血症と交感神経系の活性化が動脈硬化を促進すると考えられています。
- 心不全:睡眠時無呼吸症候群(SAS)と心不全は悪循環の関係にあり、睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者の心不全発症リスクは2.6倍、すでに心不全がある患者の死亡リスクは2倍に上昇します[23]。
関連記事
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は高血圧になりやすい?合併症やリスク、患者の特徴、治療方法を解説
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と心不全の関係とは?早期治療が命を救う理由
脳血管障害・認知機能への影響
- 脳卒中:重症睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者の脳卒中リスクは2-3倍高く、特に男性と65歳以上の高齢者で顕著です[24]。また、脳卒中後の睡眠時無呼吸症候群(SAS)合併は機能回復を遅らせることも報告されています[25]。
- 認知機能低下:長期間の睡眠時無呼吸症候群(SAS)は認知機能低下やアルツハイマー病のリスク増加と関連しています[26]。特に実行機能と記憶力への影響が大きく、治療により一部改善する可能性があります。
関連記事
睡眠時無呼吸症候群(SAS)が重症化すると死亡する?原因や生存率・寿命について解説
代謝系への影響
- 2型糖尿病:睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者は糖尿病発症リスクが1.5-2倍高く、インスリン抵抗性が増加します[27]。さらに、既存の糖尿病患者では睡眠時無呼吸症候群(SAS)の合併により血糖コントロールが不良となりやすいです[28]。
- 脂質異常症:睡眠時無呼吸症候群(SAS)は中性脂肪の上昇やHDLコレステロールの低下と関連しており、動脈硬化性疾患のリスクを高めます[29]。
日常生活への影響
- 交通事故リスク:未治療の睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者の交通事故リスクは2-7倍に上昇するとされ、特に職業ドライバーでは重大な問題となります[30]。日本では2003年に発生した山陽新幹線の居眠り運転事故を機に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニングの重要性が認識されるようになりました。
- 労働生産性の低下:睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者は集中力や判断力の低下、記憶障害などにより、職場でのパフォーマンスが約30%低下するという報告があります[31]。
- 生活の質の低下:日中の過度な眠気や疲労感、頭痛、気分障害などにより、全体的な生活の質が著しく低下します[32]。
関連記事
睡眠時無呼吸症候群(SAS)が重症化したときの症状と日常生活への影響
自分は大丈夫?セルフチェックと検査方法

睡眠時無呼吸症候群(SAS) リスク評価:セルフチェック
以下のような症状や特徴がある方は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性を考慮すべきです:
夜間の症状
- 大きないびき(特に断続的ないびき)[33]
- パートナーから「呼吸が止まる」と指摘される
- 息苦しさで目が覚める
- 夜間の頻尿(1晩に2回以上トイレに行く)
- 寝汗が多い、口・のどの乾燥
日中の症状
- 起床時の頭痛
- 日中の強い眠気(運転中、会議中など)[34]
- 集中力・記憶力の低下
- 疲労感が取れない
- イライラ感や抑うつ気分
身体的特徴
- BMI 25以上の肥満
- 首周り40cm以上(男性)、38cm以上(女性)
- 小顎症、後退顎
- 扁桃肥大
スクリーニングツール
当院では、国際的に認められた以下のスクリーニングツールを使用しています:
- エプワース眠気尺度(Epworth sleepiness Scale:ESS):日中の眠気を評価する質問票で、10点以上で過度の眠気があると判断します[35]。
- STOP-BANG質問票:いびき、疲労感、観察された無呼吸、血圧、BMI、年齢、首周り、性別の8項目を評価し、3点以上で睡眠時無呼吸症候群(SAS)リスクが高いとされます[36]。
- ベルリン質問票:いびき、日中の眠気、高血圧・肥満の有無を評価し、2カテゴリー以上が陽性の場合にリスクが高いと判断します[37]。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)診断のための検査
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の確定診断には以下の検査が行われます:
- 簡易型睡眠ポリグラフ検査(簡易PSG)
- 自宅で行える検査
- 鼻・口の気流、いびき音、酸素飽和度、体位などを測定
- AHI(無呼吸低呼吸指数)を算出し重症度を評価[38]
- 終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)
- 医療機関で一晩かけて行う精密検査 ※※自宅検査可能な機器もあり。
- 脳波、眼球運動、筋電図なども含めた詳細な評価
- 重症例や複雑な症例で実施[39]
当院では、まず簡易型睡眠検査を実施し、必要に応じて詳細な検査へと進めています。オンラインでの初診から検査キットの郵送まで対応可能です。
関連記事
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある場合はオンライン診療へ

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は非常に有病率の高い疾患でありながら、90%以上が未診断・未治療と言われています[40]。
特に、中年男性や閉経後女性、BMI 25以上の方は高リスク群であり、いびきや日中の眠気などの症状がある場合は積極的な評価が推奨されます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療により、高血圧や不整脈などの合併症リスクが大幅に低減し、日常生活の質も向上することが多くの研究で示されています[41]。
特に重症例では、治療による生命予後改善効果も報告されています[42]。
森下駅前クリニックでは、SASの診察・検査に対応したオンライン診療を行っています。
自宅からスマートフォンやパソコンで専門医に相談でき、必要に応じて簡易睡眠検査機器を宅配で受け取って自宅で測定が可能です。
24時間予約を受け付けているため、隙間時間で受診しやすいメリットがあります。
SASは適切に治療すれば、眠気が改善し、事故や合併症のリスクを大幅に減らすことができる病気です。
睡眠時無呼吸症候群かな?と思ったら、まずはお気軽に森下駅前クリニックのオンライン診療をご利用ください。
私たち専門医が、一人ひとりに合った最適な検査・治療プランをご提案し、快適な睡眠と健康な生活を取り戻すお手伝いをいたします。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療
- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?
- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します
検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?
予防
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介
合併症
症状
原因
傾向
疑い
参考文献
[1] Benjafield AV, et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med. 2019;7(8):687-698.
[2] Nakayama-Ashida Y, et al. Sleep-disordered breathing in the usual lifestyle setting as detected with home monitoring in a population of working men in Japan. Sleep. 2008;31(3):419-425.
[3] Heinzer R, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in the general population: the HypnoLaus study. Lancet Respir Med. 2015;3(4):310-318.
[4] Sutherland K, et al. Facial phenotyping by quantitative photography reflects craniofacial morphology measured on magnetic resonance imaging in Icelandic sleep apnea patients. Sleep. 2016;39(10):1749-1760.
[5] Peppard PE, et al. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. Am J Epidemiol. 2013;177(9):1006-1014.
[6] Dancey DR, et al. Impact of menopause on the prevalence and severity of sleep apnea. Chest. 2001;120(1):151-155.
[7] Malhotra A, et al. Aging influences on pharyngeal anatomy and physiology: the predisposition to pharyngeal collapse. Am J Med. 2006;119(1):72.e9-14.
[8] Malhotra A, et al. The male predisposition to pharyngeal collapse: importance of airway length. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(10):1388-1395.
[9] Bixler EO, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in women: effects of gender. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(3 Pt 1):608-613.
[10] Marcus CL, et al. Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics. 2012;130(3):e714-755.
[11] Koren D, et al. Sleep architecture and glucose and insulin homeostasis in obese adolescents. Diabetes Care. 2011;34(11):2442-2447.
[12] Young T, et al. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(9):1217-1239.
[13] Ancoli-Israel S, et al. Sleep-disordered breathing in community-dwelling elderly. Sleep. 1991;14(6):486-495.
[14] Senaratna CV, et al. Prevalence of obstructive sleep apnea in the general population: A systematic review. Sleep Med Rev. 2017;34:70-81.
[15] Li KK, et al. Obstructive sleep apnea syndrome: a comparison between Far-East Asian and white men. Laryngoscope. 2000;110(10 Pt 1):1689-1693.
[16] Redline S, et al. Racial differences in sleep-disordered breathing in African-Americans and Caucasians. Am J Respir Crit Care Med. 1997;155(1):186-192.
[17] Mihaere KM, et al. Obstructive sleep apnea in New Zealand adults: prevalence and risk factors among Māori and non-Māori. Sleep. 2009;32(7):949-956.
[18] Peppard PE, et al. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med. 2000;342(19):1378-1384.
[19] Marin JM, et al. Association between treated and untreated obstructive sleep apnea and risk of hypertension. JAMA. 2012;307(20):2169-2176.
[20] Gami AS, et al. Association of atrial fibrillation and obstructive sleep apnea. Circulation. 2004;110(4):364-367.
[21] Naruse Y, et al. Concomitant obstructive sleep apnea increases the recurrence of atrial fibrillation following radiofrequency catheter ablation of atrial fibrillation: clinical impact of continuous positive airway pressure therapy. Heart Rhythm. 2013;10(3):331-337.
[22] Gottlieb DJ, et al. Prospective study of obstructive sleep apnea and incident coronary heart disease and heart failure: the sleep heart health study. Circulation. 2010;122(4):352-360.
[23] Javaheri S, et al. Sleep apnea: types, mechanisms, and clinical cardiovascular consequences. J Am Coll Cardiol. 2017;69(7):841-858.
[24] Yaggi HK, et al. Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. N Engl J Med. 2005;353(19):2034-2041.
[25] Kaneko Y, et al. Relationship of sleep apnea to functional capacity and length of hospitalization following stroke. Sleep. 2003;26(3):293-297.
[26] Yaffe K, et al. Sleep-disordered breathing, hypoxia, and risk of mild cognitive impairment and dementia in older women. JAMA. 2011;306(6):613-619.
[27] Botros N, et al. Obstructive sleep apnea as a risk factor for type 2 diabetes. Am J Med. 2009;122(12):1122-1127.
[28] Aronsohn RS, et al. Impact of untreated obstructive sleep apnea on glucose control in type 2 diabetes. Am J Respir Crit Care Med. 2010;181(5):507-513.
[29] Coughlin SR, et al. Obstructive sleep apnoea is independently associated with an increased prevalence of metabolic syndrome. Eur Heart J. 2004;25(9):735-741.
[30] Tregear S, et al. Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med. 2009;5(6):573-581.
[31] Mulgrew AT, et al. The impact of obstructive sleep apnea and daytime sleepiness on work limitation. Sleep Med. 2007;9(1):42-53.
[32] Baldwin CM, et al. The association of sleep-disordered breathing and sleep symptoms with quality of life in the Sleep Heart Health Study. Sleep. 2001;24(1):96-105.
[33] Young T, et al. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. N Engl J Med. 1993;328(17):1230-1235.
[34] Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep. 1991;14(6):540-545.
[35] Johns MW. Reliability and factor analysis of the Epworth Sleepiness Scale. Sleep. 1992;15(4):376-381.
[36] Chung F, et al. STOP-Bang questionnaire: a practical approach to screen for obstructive sleep apnea. Chest. 2013;143(6):1631-1637.
[37] Netzer NC, et al. Using the Berlin Questionnaire to identify patients at risk for the sleep apnea syndrome. Ann Intern Med. 1999;131(7):485-491.
[38] Collop NA, et al. Clinical guidelines for the use of unattended portable monitors in the diagnosis of obstructive sleep apnea in adult patients. J Clin Sleep Med. 2007;3(7):737-747.
[39] Kapur VK, et al. Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult Obstructive Sleep Apnea: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med. 2017;13(3):479-504.
[40] Young T, et al. Estimation of the clinically diagnosed proportion of sleep apnea syndrome in middle-aged men and women. Sleep. 1997;20(9):705-706.
[41] Marin JM, et al. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet. 2005;365(9464):1046-1053.
[42] Campos-Rodriguez F, et al. Cardiovascular mortality in women with obstructive sleep apnea with or without continuous positive airway pressure treatment: a cohort study. Ann Intern Med. 2012;156(2):115-122.