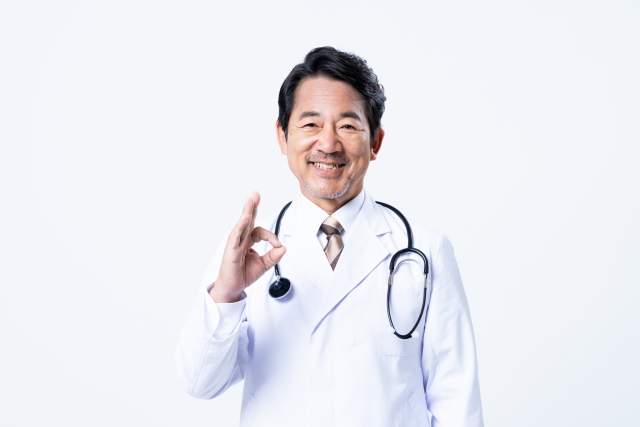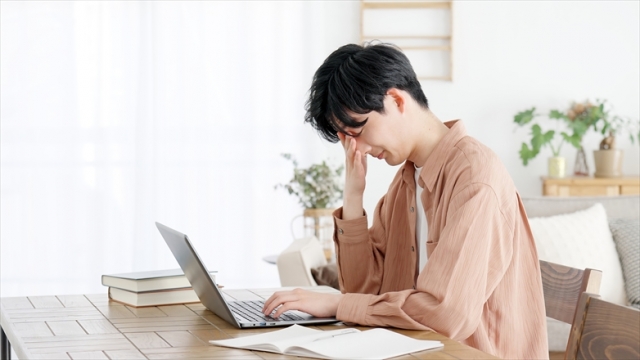夜間に突然体が動かなくなる「金縛り」を経験したことがある方も多いでしょう。金縛りは恐ろしく不思議な現象に思えますが、医学的には睡眠麻痺と呼ばれる睡眠現象です。
特に中高年の方の中には、「自分の金縛りは睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因ではないか?」と心配される方もいます。実際、睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は一晩に何度も呼吸が止まる病気で、睡眠の質を大きく損ないます。睡眠が障害されれば金縛りが起こりやすくなる可能性も考えられます。本記事では、金縛り(睡眠麻痺)とは何か、SASとの関連性、そしてSASが金縛りを招く理由やSASのサインと治療法について、最新の医学エビデンスに基づきわかりやすく解説します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
金縛り(睡眠麻痺)とは?そのメカニズムと原因

金縛りとは、寝入りばなや目覚め際に意識があるのに身体を動かせなくなる現象です。多くの場合、数十秒から数分で自然に解除されます。医学的には「睡眠麻痺」と呼ばれ、レム睡眠(身体が麻痺し夢を見ている睡眠段階)と覚醒状態の狭間で生じる一種の睡眠障害(パラソムニア)です。レム睡眠中は夢を演じないよう脳が筋肉を麻痺させていますが、金縛りでは脳が半分目覚めたのに筋肉の麻痺だけが解けていないために起こります。この間、息苦しさや「誰かに押さえつけられている」ような幻覚を感じることもあり、大変な恐怖を伴います。しかし身体への危険はなく、しばらくすれば自然に体の動きが戻ります。
金縛りが起こる原因は完全には解明されていませんが、不規則な睡眠や睡眠不足、強いストレスなどが誘因とされています。またうつ病や不安障害など精神的ストレス、あるいはナルコレプシー(居眠り発作)といった睡眠疾患に伴うこともあります。実際、多くの人が人生で一度は金縛りを経験するとされ、その頻度は全人口の20〜30%とも報告されています。つまり金縛り自体は珍しいものではなく、単発で起こる限り大きな問題にはなりません。ただし繰り返し頻発する場合は、その背景に他の睡眠障害が隠れている可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は金縛りの直接の原因?その関連性は?

では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)は金縛りを引き起こすのでしょうか?結論から言えば、SASが金縛りの“直接の原因”であると科学的に断定することはできません。金縛りとSASはそれぞれ独立した睡眠障害ですが、関連性が示唆される研究報告はあります。
たとえば、閉塞型SAS患者では一般人に比べて金縛りを経験する割合が高いとのデータがあります。一つの研究では、SAS患者の約38%が金縛りを経験していたのに対し、SASでない人ではその割合が5〜20%程度だったと報告されています(台湾での患者対象研究)。この数字から、一見するとSASのある人で金縛りが多いように思えます。
しかし注意したいのは、これは因果関係ではなく相関関係に過ぎないという点です。つまり、「SASだから必ず金縛りになる」わけでも「金縛りがあるから必ずSASである」わけでもありません。実際、研究によって結果は様々で、SASの有無と金縛り発生との間に明確な因果関係は認められていないのが現状です。対象者の睡眠衛生やストレス状態など他の要因が影響している可能性も高く、SASがあっても金縛りを全く経験しない人も多いのです。要するに、SASが金縛りの直接の原因であるとまでは言い切れないということです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)が「金縛り」を招く可能性のある理由

直接の因果関係は明確でないものの、SASが間接的に金縛りを誘発しやすくする要因はいくつか考えられます。
- 睡眠の分断と睡眠不足:SASの患者さんは、睡眠中に何度も無呼吸や低呼吸による覚醒反応が起こります。その結果、睡眠が細切れになり慢性的な睡眠不足に陥りがちです。睡眠不足は金縛りの大きな誘因であり、SASによる睡眠不足が金縛り発生リスクを高めると考えられます。
- レム睡眠からの中途覚醒:SASでは特にレム睡眠中に無呼吸発作が悪化しやすいことが知られています。レム睡眠時に無呼吸で酸素不足になると、脳が危機的状況と判断して半ば強制的に目覚めさせます(睡眠中の覚醒反応)。この「レム睡眠中に急に目覚める」状況は、ちょうど金縛りが起こりやすいタイミングです。脳が覚醒しても身体がまだレム睡眠の麻痺状態にあるため、無呼吸による覚醒が金縛り発作となって表れる可能性があります。
- 睡眠姿勢の影響:仰向け(上向き)で寝ると金縛りが起こりやすいことが報告されています。ある調査では、金縛りエピソードの約60〜80%が仰向け睡眠中に発生していました。一方でSASも仰向けで悪化しやすく、舌根が喉に落ち込み気道が塞がりやすくなります。そのため、仰向け睡眠の習慣をもつSAS患者さんでは金縛りも起こりやすくなるかもしれません。
- 共通の誘因:SASと金縛りには共通する誘因も多くあります。例えばアルコールや睡眠薬の使用は気道の筋肉を弛緩させてSASを悪化させますが、中枢の覚醒反応にも影響し金縛りを誘発しやすくします。また不規則な睡眠習慣や交代勤務も、SASと金縛り双方のリスク因子です。SAS患者さんは夜間の度重なる中途覚醒によって生活リズムが乱れがちであり、そのことが金縛り体験につながる可能性があります。
以上のように、SASそのものが直接金縛りを“起こす”というより、SASによって悪化する睡眠環境(睡眠不足・断片化やレム中途覚醒など)が結果的に金縛りを誘発しやすくなると考えられます。したがって、金縛りに悩む方はその背景にSASなど睡眠の質を低下させる要因がないか確認することが大切です。
金縛りと一緒にチェック!睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的なサイン

慢性的に金縛りが起きる場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインがないか確認してみましょう。SAS患者さんによく見られる典型的な症状には以下のようなものがあります:
- 大きないびき(睡眠中の激しいいびき。家族やパートナーから指摘される)
- 睡眠中の無呼吸(寝ている間に呼吸が止まっていると指摘される)
- 夜中に息苦しくて目が覚める(「溺れるような感じ」で突然目覚めることがある)
- 起床時の頭痛やだるさ(朝起きたときに頭痛、熟睡できていない感じが強い)
- 日中の強い眠気(十分寝たはずなのに日中に耐え難い眠気がある)
これらはSASで典型的にみられるサインです。特に大音量のいびきや睡眠中の呼吸停止はSASを強く示唆する症状です。夜間に何度も目が覚めたり(トイレに起きる回数が多い)、日中の集中力低下や居眠り運転のリスクが高まっている場合も注意が必要です。金縛りだけでなく、こうしたSASの症状に心当たりがある場合は放置せず専門医に相談することをお勧めします。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療

睡眠時無呼吸症候群は適切な治療によって症状を改善できる疾患です。治療の主な目的は、睡眠中の無呼吸を無くし十分な酸素を確保すること、そして質の良い継続的な睡眠を取り戻すことにあります。患者さんの状態に応じて、以下のような治療法が組み合わされます。
- 生活習慣の改善:SASの大きな危険因子である肥満に対しては減量が不可欠です。適度な運動や食事管理により体重を落とすことで、気道周囲の脂肪沈着が減り無呼吸が緩和します。また飲酒や喫煙、睡眠薬の使用を控えること、規則正しい睡眠習慣を維持することも重要です。アルコールや睡眠薬は筋肉を弛緩させ無呼吸を悪化させるため、就寝前は避けましょう。軽症の方では、横向きで寝るなど睡眠姿勢の工夫で症状が改善する場合もあります。
- CPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法):中等度〜重度のSASに対する第一選択の治療法です。就寝時に鼻マスクから気道に空気を送り込み、気道を陽圧で押し広げた状態で維持することで無呼吸を防止します。CPAP療法により睡眠中の低酸素状態が解消され、日中の眠気も大幅に改善します。実際、CPAPは偽治療と比較して呼吸障害指数の大幅な低下と日中の眠気改善効果が証明されており、国際的なガイドラインでも強く推奨されています。
- マウスピース治療(口腔内装置):下顎を前方に固定する特殊なマウスピースを就寝時に装着し、喉の気道スペースを広げて無呼吸を軽減する治療です。軽症〜中等症のSASや、CPAPがどうしても継続困難な場合に用いられます。マウスピースでも無呼吸指数の改善や日中の眠気軽減に効果がありますが、無呼吸の抑制効果自体はCPAPに劣ることが報告されています。適応となるかは歯科的な評価も含め専門医と相談して決めます。
- 外科的治療:解剖学的な気道狭窄の原因が明確な場合(例えば極度の扁桃肥大や鼻中隔の重度湾曲など)には、耳鼻科領域の手術で原因を除去することで症状改善が期待できます。ただしSAS全体から見ると手術適応となるケースは限られており、まずは上記の保存的治療が優先されます。最近では、重症例に対し舌下神経刺激装置(Hypoglossal Nerve Stimulator)の埋め込みといった新しい治療法も登場していますが、適応や長期効果については専門医による評価が必要です。
これらの治療によって、多くのSAS患者さんは症状のコントロールが可能です。実際、適切な治療で夜間の無呼吸が解消すれば、結果として金縛りの頻度も減少することが期待できます。質の良い睡眠が確保されれば、レム睡眠中の異常な覚醒現象(=金縛り)は起こりにくくなるためです。SASの治療はご自身の睡眠の質と日中の生活の質(QOL)を高めるだけでなく、金縛りの予防にもつながると言えるでしょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある場合はオンライン診療へ

「忙しくて病院に行く時間がない」「まずは手軽に相談したい」という方には、オンライン診療の利用もおすすめです。
森下駅前クリニックでは、SASの診察・検査に対応したオンライン診療を行っています。
自宅からスマートフォンやパソコンで専門医に相談でき、必要に応じて簡易睡眠検査機器を宅配で受け取って自宅で測定が可能です。
24時間予約を受け付けているため、隙間時間で受診しやすいメリットがあります。
SASは適切に治療すれば、眠気が改善し、事故や合併症のリスクを大幅に減らすことができる病気です。
長期間にわたって眠気が取れないと悩んでいる場合や、いびき・無呼吸の指摘がある方は、早めに専門医に相談し、必要な検査・治療を受けて快適な睡眠と日常生活を取り戻しましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
参考文献
- Cleveland Clinic. Sleep Paralysis: What It Is, Causes, Symptoms & Treatment. (2023)
- Sleep Foundation. Sleep Paralysis: Symptoms, Causes, and Treatment. (更新日: 2023年7月26日)
- Hsieh SW, et al. Isolated sleep paralysis linked to impaired nocturnal sleep quality and health-related quality of life in Chinese-Taiwanese patients with obstructive sleep apnea. Qual Life Res. 2010;19(9):1265-1272.
- Cleveland Clinic. Sleep Apnea: What It Is, Causes, Symptoms & Treatment. (2024)
- Qaseem A, et al. Management of Obstructive Sleep Apnea in Adults: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2013;159(7):471-483
- Akashiba T, et al. Sleep Apnea Syndrome (SAS) Clinical Practice Guidelines 2020 (English ver.). Respir Investig. 2022;60(1):3-32.
- Denis D, et al. A systematic review of variables associated with sleep paralysis. Sleep Med Rev. 2018;38:141-157.
睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療
- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?
- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します
検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?
予防
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介
合併症
症状
原因
傾向
疑い