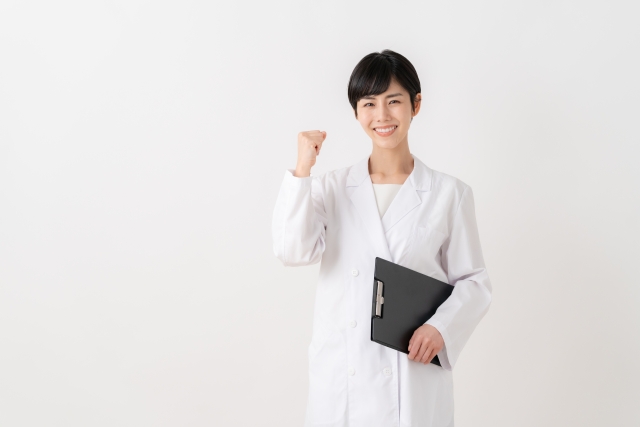睡眠時無呼吸症候群(SAS)に対する代表的な治療であるCPAP療法では、「AHI(無呼吸低呼吸指数)」という指標が治療効果を判断する上で重要です。
AHIとは一体何なのか、CPAP使用中はAHIをどの程度まで下げることが目標になるのか。
そして、CPAPをしっかり使っているのにAHIがなかなか下がらない場合に考えられる原因や具体的な改善策について、最新のエビデンスを踏まえて専門医がわかりやすく解説します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
そもそもAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?睡眠の質を示す重要な指標

AHI(Apnea Hypopnea Index)とは、睡眠1時間あたりに何回の無呼吸(10秒以上の呼吸停止)や低呼吸(低下した呼吸)が生じたかを表す指数です。
簡単に言えば、睡眠中の呼吸の乱れの頻度を示すもので、この数値が高いほど睡眠の質が損なわれている可能性があります。
AHIは一晩の睡眠ポリグラフ検査で測定され、AHI=(無呼吸+低呼吸の合計)÷睡眠時間(時間)という計算式で求められます。
AHIの値により、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重症度分類が行われます。
一般的にAHI 5未満が正常範囲(SASではない)とされ、5以上で睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
その上でAHIが5以上15未満なら「軽症」、15以上30未満が「中等症」、30以上は「重症」と定義されています。
例えばAHIが30を超える重症の方では、1時間に30回以上も呼吸が止まったり浅くなったりしていることになり、日中の強い眠気や血中酸素低下による様々な健康リスクが高まります。
なお、CPAP装置には使用中のAHIを記録・表示する機能が備わっており、CPAP療法中のAHIはその治療効果を測る一つのバロメーターになります。
CPAP適応前の検査でAHIが高かった方でも、CPAPを毎晩適切に使用することでこの数値が大幅に下がります。
AHIがしっかり低下していれば、「空気の圧力で気道が十分に開いて確保され、無呼吸や低呼吸がほとんど防げている」ことを意味します。
一方、CPAP使用時のAHIが高いままの場合は、治療が不十分な可能性があります。
正常成人のAHIは5未満ですので、CPAPによって少なくとも5未満の値に抑えられることが理想です。
CPAP治療におけるAHIの目標値は「5未満」が目安

CPAP治療中のAHI目標値は一般的に5未満が目安とされています。
AHI 5未満であれば正常範囲内であり、睡眠時無呼吸症候群としては十分にコントロールされた状態と判断できます。
実際、CPAP治療を受ける成人ではAHIを5未満に抑えることが一つのゴールになります。
AHIが5未満まで下がれば、多くの方で日中の眠気や倦怠感など症状の改善が期待できるほか、無呼吸による長期的な合併症リスクも軽減できると考えられます。
ただしAHIの目標値は一律ではなく、年齢や体調、もとの重症度によって若干異なる場合があります。
例えば重症OSA(閉塞性睡眠時無呼吸)の患者さんでは、CPAP導入前はAHIが数十以上と極めて高値であることもあります。
そのような場合、CPAP治療によってAHIが劇的に低下しても、わずかに5を上回る程度の軽症レベルが残ることがあります。
このような患者さんでは症状が十分改善し日中にすっきり過ごせるのであれば、厳密にAHI<5に達していなくても容認されることがあります。
また高齢者や持病のある方では、副作用を避けるためCPAPの圧力設定に上限がある場合もあり、無理にAHIをゼロ近くまで下げることより患者さん個々にとってバランスの良い目標値を設定することが大切です。
いずれにせよ、最終的なAHI目標は担当医と相談の上で決めることになります。
多くの方は治療前より大幅にAHIが下がり、症状や健康状態が改善するレベルまで減少します。
要注意!CPAPを使ってもAHIが下がらない・高いままの主な原因7選

マスクからの空気漏れ(リーク)
CPAPマスクのフィットが悪かったり、古くなって劣化したマスクを使用していると、睡眠中にマスクと顔の隙間から空気が漏れることがあります。必要な空気圧が気道に十分届かないため、気道の開存性が保てず無呼吸・低呼吸が残存してしまい、AHIが高止まりする原因になります。
リークはCPAP治療のつまずきとして非常に一般的で、就寝中に自覚なく起こり得ます。
メーカーのデータによれば、マスク漏れの主な原因は「マスクのサイズ・装着の不適合」「汚れの付着」「口からの空気漏れ」の3つとされています。
まずはマスクを正しい位置に装着しストラップを調整することで、空気漏れが最小になるよう確認しましょう。
長期間使ったマスクはクッション部がへたって密閉性が落ちますので、定期的な交換も大切です。
また就寝中の体位変換でマスクがずれて漏れが生じることもあります。漏れが多い夜はCPAP装置のAHI計測も精度が落ちる可能性が指摘されています。
マスクからの空気漏れを防ぐことがAHI低下の第一歩です。
マスクの種類が合っていない
CPAPマスクには鼻だけを覆う「鼻マスク」や鼻孔に差し込む「ピローマスク」、口と鼻を両方覆う「フルフェイスマスク」などがあります。
患者さんの顔の形や呼吸の癖によって適したマスクは異なります。
自分に合わないタイプのマスクを使っていると、装着感の悪さから空気漏れが生じやすかったり、必要とする空気圧が高くなりがちです。
実際、フルフェイスマスクは鼻マスクに比べて治療効果がやや劣る可能性が指摘されています。
マスクの種類によって治療成績に差が出るため、現在のマスクが合わないと感じる場合は別タイプを試す価値があります。
口呼吸になっている(鼻マスク・ピローマスクの場合)
鼻のみを覆うタイプのマスク(鼻マスクやピローマスク)を使用中の方に多い原因です。
就寝中に口が開いて口呼吸になると、CPAPで送られた空気が口から漏れてしまい、気道内圧が保てなくなります。
その結果、無呼吸・低呼吸が十分防げずAHIが高めに残ってしまいます。
鼻マスク装着中に口呼吸になると、朝起きた時に口や喉が乾燥していることが多く、これが一つのサインです。
対策としては、あごベルトを使用して睡眠中に口が開かないよう軽く固定する方法があります。
また、口呼吸自体を防ぐ根本策として、日中から鼻呼吸を意識するトレーニングや、就寝前に鼻腔をスプレーや洗浄で清潔に保つことも有効です。
どうしても口呼吸が治らない場合は、フルフェイスマスクへの変更も検討しましょう(口と鼻の両方に空気が送られるため、口が開いても治療効果が落ちにくくなります)。
設定圧が不適切
CPAP装置の空気圧(陽圧)の設定が、その人にとって適切でない場合もAHIが下がらない原因になります。
圧力が低すぎれば気道を十分に開くことができず、一部の無呼吸や低呼吸が残存します。
特にCPAP導入後に体重増加や上気道の状態悪化があった場合、当初の圧力では足りなくなることがあります。
逆に圧力が高すぎる場合、必要以上の不快感を生じて睡眠を妨げたり、過換気による中枢性無呼吸を誘発してしまうことがあります。
機種によっては自動調節式(APAP)のCPAPもあり、必要圧が変動する方には有用ですが、それでも合わない場合は再度専門医に相談して設定圧の見直しが必要です。
体重の増加
体重増加(肥満の進行)は睡眠時無呼吸を悪化させる大きな要因です。
首周りや舌の脂肪沈着によって気道が狭くなり、無呼吸が起こりやすくなります。
CPAP治療中でも、体重が増えると以前より高い空気圧が必要になる場合があり、設定を変えていなければAHIが悪化することがあります。
10%の体重増加によりAHIが約32%も増加したとの研究報告があります。
逆に言えば、体重を減らすことでAHIを下げられる可能性があります。
CPAPを始めた後に体重が増えてしまったという方は、治療効果維持のためにも生活習慣を見直し、減量に取り組むことが重要です。
飲酒・喫煙・睡眠薬
アルコールの摂取や一部の薬剤(睡眠導入剤や麻酔薬)は筋肉を弛緩させ、睡眠中の気道をより塞ぎやすくします。
また脳の呼吸中枢も抑制されるため、無呼吸に対する体の覚醒反応が鈍くなり、呼吸停止が長引く傾向があります。
その結果、普段よりAHIが上昇してしまうことが知られています。
喫煙もまた、咽頭や鼻粘膜の炎症・腫脹を引き起こし気道抵抗を増やすため、無呼吸悪化の一因となります。
以上より、就寝前の飲酒や過度の喫煙、必要以上の睡眠薬使用は避けることが望ましく、CPAP治療中のAHIを下げるためには生活習慣の改善が重要です。
中枢性無呼吸(CSA)の出現
CPAP治療によって閉塞性の無呼吸は改善しても、代わりに中枢性無呼吸が生じてAHIが下がりきらないケースがあります。
これは「治療により気道は確保されたが、脳の呼吸中枢から呼吸の指令が一時的に止まってしまう」現象で、治療に誘発された中枢性無呼吸(Complex Sleep Apnea)とも呼ばれます。
CPAP開始直後の患者さんの2〜20%程度にこの中枢性無呼吸の出現が認められていますが、多くは数週間〜数ヶ月の経過で消失します。
一部の患者さんでは持続することがあります。
中枢性無呼吸はCPAPの空気圧設定が高すぎる場合や低すぎる場合にも誘発されやすいことが知られており、原因4で述べた圧設定不適と関連することもあります。
このような睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、通常のCPAPでは対処が難しいため専門的対応が必要です。
具体的には圧力設定の微調整や高度な自発呼吸同調技術を持つASV装置への変更などが検討されます。
中枢性無呼吸が原因の場合、ご自身で判断するのは難しいため、早めに主治医に相談しましょう。
以上、CPAP使用中にAHIが下がらない主な原因7つを挙げました。該当するものがあれば次章の対策を講じることで改善する可能性があります。
専門医が教えるAHIを改善するための具体的な対策

まずはセルフチェック!自分でできる改善策
AHIが思うように下がらない場合、まずはご自身で以下のポイントをセルフチェックしてみましょう。日々のCPAP療法の質を高めることで、AHI改善につながる可能性があります。
マスクのフィッティングを見直す
就寝前にマスクを正しく装着できているか確認しましょう。鏡を見ながら位置合わせし、ストラップの緩みや歪みがないよう調整します。
空気を出した状態で手を当て、漏れがないか確かめてみてください。
必要に応じてマスククッションの交換やストラップの劣化チェックも行います。
適切にフィットしたマスクは空気漏れを最小限にし、AHI低下に直結します。
ご自身に合ったマスクタイプを選ぶ
現在お使いのマスクがどうにも合わない場合、思い切って別のタイプのマスクを試すことも検討しましょう。
例えば鼻マスクでどうしても口呼吸になる方はフルフェイスマスクに変更する、逆にフルフェイスで漏れが多い方は鼻マスク+あごベルトに挑戦する、といった方法です。
一般に鼻マスクやピローマスクは装着感が軽くリークも少ない傾向があります。
可能であれば鼻呼吸のトレーニングをしつつ、軽量な鼻マスクで治療するのが望ましいでしょう。
反対に重度の鼻閉がある方は無理に鼻マスクに固執せず、口も使えるフルフェイス型で確実に気道を開通させるほうが効果的な場合もあります。
睡眠専門クリニックでは様々な種類のマスクを試着できるところもありますので、遠慮なく相談してください。
口呼吸への対策を講じる
鼻マスク使用中の方は口テープやあごベルトを活用してみましょう。
市販の口閉じテープや顎支持バンドを使うことで、睡眠中の不顕性の口開きをかなり防ぐことができます。
特に「朝喉がカラカラ」「CPAP中もいびきを指摘される」という方には有効です。
また就寝前の鼻ケアも重要です。鼻炎がある方は寝る前に点鼻薬で鼻腔を開通させ、湿度設定付きCPAPなら適切な湿度を保つことで鼻づまりを減らせます。
鼻がしっかり通れば口呼吸も起こりにくくなり、一晩中CPAPの効果が発揮されやすくなります。
生活習慣を見直す
AHI改善のためには生活習慣の是正も欠かせません。
特に寝酒(就寝前の飲酒)は睡眠の質を下げ無呼吸を悪化させますし、喫煙習慣も長期的に見てSASのリスク要因です。
睡眠薬も必要最低限の量にとどめ、可能であれば主治医と相談の上減薬を検討してください。
夜間のカフェイン摂取も避け、規則正しい睡眠習慣を心がけることがCPAP治療効果を高めます。
これらの取り組みは地味に思えますが、継続すればAHIや日中症状の改善につながる可能性があります。
体重管理(減量)に努める
前述のように肥満と無呼吸の程度は密接に関連しています。
CPAP治療中であっても、体重が減ればAHIがさらに下がり、逆に増えればAHIが悪化する傾向があります。
ぜひ食事療法や適度な運動によって体重管理を行いましょう。
10%の減量でもAHIが約26%改善するとの研究結果があります。
CPAPは根本治療ではなく対症療法ですので、肥満が原因の場合は減量こそが根治への近道です。
主治医や栄養士のサポートを受けながら無理なく減量計画を立てましょう。
CPAPの使用状況を再確認する
基本的なことですが、CPAPを毎晩できるだけ長時間使用することも大切です。
1晩あたり4時間以上、可能なら就寝から起床まで装着し続けることで最大の効果が得られます。
装着を怠った時間帯には無呼吸が再発してしまうため、たとえ昼寝でもCPAPを使うことが推奨されます。
CPAPの装着感がどうしても辛い場合は無理せず専門医に相談し、機種の変更や加湿器の導入など快適性向上の工夫をしてもらいましょう。
以上のセルフチェック・対策を実践することで、多くの方はAHIの改善が期待できます。
特にマスク装着の工夫と生活習慣の改善は効果が大きいので、できる範囲から取り組んでみてください。
セルフチェックで改善しない場合は、すぐに専門医へ相談を
上記の対策を講じてもなおAHIが高値で推移する場合や、自分では原因が特定できない場合は、できるだけ早めに主治医(睡眠専門医)へ相談しましょう。
医師はCPAP装置に記録された詳細データ(AHIの内訳、漏れ量、いびき指数、脈拍や呼吸パターンなど)を解析し、問題点に応じた適切な処置を行います。
例えば残存する無呼吸が閉塞性であれば圧力設定の増加やマスク再調整を検討しますし、中枢性イベントが多ければ圧力の再調節や高度なPAP装置(BiPAPやASV)の適応を判断します。
機器の不具合が疑われる場合はメーカーと連携し、装置交換や設定変更を行うこともあります。
また患者さん自身が気付かないCPAP使用上の問題(例えば無意識に夜間マスクを外してしまっている、など)が潜んでいないか問診で確認し、必要に応じて対策を助言します。
特にAHIが10以上といった中等度以上の残存無呼吸が続く場合や、AHIは低いのに症状が改善しない場合は注意が必要です。
何らかの見落としや別の睡眠障害(例:周期性四肢運動、睡眠不足症候群など)が併存している可能性もあります。
自己判断せず、専門医の評価を仰ぐことで、安全かつ効果的な治療へ軌道修正できます。
CPAP療法は機械相手の治療ですが、医師との二人三脚で調整を重ねていくことが成功の鍵です。
不安な点があれば些細なことでも遠慮なく医師に相談してください。
AHIの改善にはオンライン診療が効果的

AHIを適切に改善していくためには、定期的なフォローアップと迅速な対応が重要です。
そこで活用したいのがオンライン診療(遠隔医療)です。
オンライン診療を利用すれば、自宅にいながら専門医の診察やアドバイスを受けることができ、CPAP治療の質を維持・向上させるのに役立ちます。
特に最近のCPAP装置は通信機能やクラウド記録を備えているものも多く、医師が遠隔で患者さんのAHIや装着時間、リーク量などのデータを把握できます。
これにより、異常の早期発見と迅速な対策が可能です。
例えば「ここ数日AHIが上がっている」「リークが増えている」といった変化にも気付けます。
実際、オンラインによるCPAP患者支援の有効性は研究でも示されています。
複数のランダム化比較試験をまとめたメタ分析では、遠隔モニタリングやオンライン指導を行ったグループでは従来型フォローに比べてCPAPの平均使用時間が1日あたり約30分延長し、4時間以上の使用継続率も有意に向上しました。
わずかな差に思えますが、長期的には睡眠の質や合併症リスクに影響し得る貴重な延長です。
CPAP療法は「どれだけ毎晩使えるか」が成果に直結しますので、オンライン診療によって患者さんのモチベーション維持や不安解消を図り、結果的にAHIのさらなる低減につなげることが期待できます。
さらにオンライン診療であれば通院の手間が省け、悪天候や体調不良の日でも自宅から安全に受診できます。
対面診察では伝えにくい些細な悩みも、ビデオ通話越しならリラックスして相談できるという声もあります。
こうした利便性の高さも継続治療には大切な要素です。
CPAP治療は長期戦ですから、「困った時にすぐ相談できる」環境があること自体が患者さんの安心感につながり、治療継続率アップ→AHI改善につながるのです。
このようにオンライン診療はAHIの改善・管理にとって有力な手段です。
特にお忙しい方や通院が難しい方でも、オンラインなら隙間時間に専門医のフォローを受けられます。
遠隔でも医師と二人三脚のサポート体制を築き、CPAP療法を最大限に活用していきましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある場合はオンライン診療へ

「もしかして自分は睡眠時無呼吸症候群では?」と感じている方や、いびき・無呼吸を指摘されて心配な方は、まずは専門医に相談することが肝心です。
最近はオンライン診療で気軽に専門相談を受けることも可能です。
当院でも睡眠時無呼吸症候群(SAS)のオンライン診療を積極的に行っています。
遠方の方や多忙な方でもご自宅から専門医の診察を受けられ、必要に応じて簡易検査の手配やCPAP導入までスムーズにサポートいたします。
少しでもSASの疑いがある方は、ぜひ一度オンライン診療をご利用ください。
放置された無呼吸は体に大きな負担をかけます。
早期発見・早期治療で、いびきのない快適な睡眠と健康な日中生活を取り戻しましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療
- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?
- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します
検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?
予防
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介
合併症
症状
原因
傾向
疑い
参考文献:
Cleveland Clinic: “Apnea-Hypopnea Index (AHI): What It Is & Ranges.” Cleveland Clinic Health Library.
ResMed公式ブログ: “Why does my apnea–hypopnea index (AHI) change?” (19 Nov 2024).
Gonçalves MAほか. “Comparing CPAP masks during initial titration for OSA: one-year experience.” Braz J Otorhinolaryngol. 2022;88(S5):suppl5: (doi: 10.1016/j.bjorl.2021.10.007)
Peppard PE et al. “Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disordered breathing.” JAMA. 2000;284(23):3015-21.
Kolla BP et al. “The Impact of Alcohol on Breathing Parameters during Sleep: A Systematic Review and Meta-analysis.” Sleep Med Rev. 2018 Dec;42:59-67.
Javaheri S, Smith J, Chung E. “The prevalence and natural history of complex sleep apnea.” J Clin Sleep Med. 2009;5(3):205-211.
Labarca G et al. “Telemedicine interventions for CPAP adherence in obstructive sleep apnea patients: Systematic review and meta-analysis.” Sleep Med Rev. 2021;60:101543.