
睡眠時無呼吸症候群の手術について気になっているあなたへ
※当院では手術の対応を行っておりません。
「睡眠時無呼吸症候群(SAS)って診断されたけど、手術なんて本当に必要なの?」 多くの方がそう思われるでしょう。実際に、私のクリニックにも、不安な表情で相談に来られる患者さんが後を絶ちません。 例えば、こんな方がいました。
- Aさん(50代男性):日中の眠気がひどく、仕事に集中できない。CPAP治療を試みたが、マスクの締め付け感が我慢できなかった。
- Bさん(40代女性):いびきがうるさいと家族から指摘され、SASと診断された。肥満はなく、手術で根本的に治したいと考えている。
お二人とも、SASの症状や治療に対する希望は全く異なります。Aさんのように、CPAP治療が合わないと感じる方もいれば、Bさんのように、身体的な負担の少ない治療を希望される方もいます。
重要なのは、SASと一言で言っても、その症状や重症度は人それぞれであり、最適な治療法も異なるということです。 そして、手術が必要かどうかは、病気の程度や症状、年齢、生活習慣、そして患者さん自身の希望などを総合的に判断する必要があります。
「手術」と聞くと思い切って決断しなければならないと感じるかもしれませんが、まずはご自身の症状や治療法について、医師に相談することから始めましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術は、まるで家の換気扇を取り付けるように、狭くなった気道を広げて呼吸を楽にするための方法です。
しかし、すべての患者さんに同じ換気扇が合うわけではありませんよね?
例えば、鼻中隔彎曲症という、鼻の真ん中の壁が曲がっているせいで鼻呼吸がしにくい方がいるとします。この方は、鼻中隔矯正術という、曲がった壁をまっすぐにする手術を受けることで、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が改善する可能性があります。
この場合、原因となっている鼻の詰まりが解消されれば、手術によってSASが完治することも期待できます。
一方、扁桃肥大やアデノイド肥大など、喉の奥の組織が大きくなって気道を塞いでいる場合は、これらの組織を切除する手術が行われます。しかし、手術後も生活習慣の乱れや加齢などによって再び肥大してしまうこともあり、その場合は再発の可能性も考えられます。
さらに、肥満が原因で気道が圧迫されている場合は、たとえ手術で気道を広げても、体重管理が不十分であれば、再び症状が出てしまう可能性があります。これは、換気扇を取り付けても部屋の空気が澱んでしまうのと同じです。
このように、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術が完治に繋がるかどうかは、原因、症状、手術方法、そして術後の自己管理など、様々な要因によって異なってきます。 また、酸素飽和度指数(ODI)という指標を用いることで、手術の必要性をより正確に見極めることができます。
ODIは、睡眠中にどれくらい酸素濃度が低下するかを示す指標で、4% ODI≧15イベント/時間の場合、成人OSAと診断され、手術が検討されることが多いです。 手術はあくまで症状を改善するための選択肢の一つであり、魔法のように必ず完治するわけではありません。
専門の医師とじっくり相談し、あなたにとって最適な治療法を選択することが大切です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術治療
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術治療は、大きく分けて7つの種類があります。それぞれの治療法の特徴を理解して、自分に合った治療法を選びましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術治療は、大きく分けて7つの種類があります。それぞれの治療法の特徴を理解して、自分に合った治療法を選びましょう。
上下顎同時前進術
上下顎同時前進術は、上顎と下顎を同時に前方に移動させる手術です。イメージとしては、あご全体を前にずらし、気道のスペースを広げるような感じです。 メリット
- 効果が持続しやすい: 骨格レベルで気道を広げるため、手術の効果が長持ちしやすいというメリットがあります。
- SASの症状を大幅に改善できる可能性: 気道が大きく広がるため、中等度~重度のSASにも効果が期待できます。特に、顎が小さい、あるいは後退しているために気道が狭くなっている患者さんに向いています。
デメリット
- 手術が大掛かりになる: 上下顎の骨を切断して移動させるため、手術は大掛かりになり、全身麻酔が必要になります。
- 回復に時間がかかる: 手術後は、腫れや痛みがしばらく続くことがあります。また、食事や会話がしにくくなる場合もあり、社会復帰までに時間がかかることがあります。
- 顔貌が変化する可能性: 顔貌が変化する可能性があります。手術前に、医師と顔貌の変化についてよく相談しておくことが大切です。
費用: 保険適用で約10万円~30万円(3割負担の場合) 入院期間: 約1週間~2週間 ※おおよその目安であり、各医療機関により異なります。
口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)
口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)は、「のどちんこ」と呼ばれる口蓋垂と、その周辺の粘膜である軟口蓋の一部を切除したり、形状を変えたりする手術です。 メリット
- 体への負担が比較的少ない: 上下顎同時前進術と比べて、体への負担が少なく、回復も早いというメリットがあります。
- 回復が早い: 手術後、比較的短期間で日常生活に戻ることができます。
デメリット
- 効果が限定的: 気道の閉塞が強い場合や、扁桃腺が大きい場合は、UPPPだけでは十分な効果が得られないことがあります。
- 再発する可能性: 軟口蓋が再びたるんでしまい、症状が再発することがあります。
費用: 保険適用で約5万円~10万円(3割負担の場合) 入院期間: 約3日~5日 ※おおよその目安であり、各医療機関により異なります。
オトガイ舌筋前進術
オトガイ舌筋前進術は、舌の付け根にあるオトガイ舌筋という筋肉を、あごの先端にある骨(オトガイ)と一緒に前に移動させる手術です。 舌が喉の奥に落ち込んで気道を塞いでしまうのを防ぎ、気道を広げます。 メリット
- 中等度以上のSASに効果: 中等度以上のSASに効果が期待できます。
デメリット
- 顔貌が変化する可能性: 顔貌が変化する可能性があります。手術前に、医師と顔貌の変化についてよく相談しておくことが大切です。
- 口の中に違和感: 手術後、口の中に違和感を感じることがあります。
費用: 保険適用で約10万円~20万円(3割負担の場合) 入院期間: 約1週間~2週間 ※おおよその目安であり、各医療機関により異なります。
レーザー口蓋垂軟口蓋形成術(LAUP)
レーザー口蓋垂軟口蓋形成術(LAUP)は、レーザーを使って口蓋垂や軟口蓋を縮小させる手術です。高周波エネルギーを用いて、粘膜を蒸発させたり、凝固させたりすることで、口蓋垂や軟口蓋を小さくします。 メリット
- 体への負担が少ない: UPPPよりもさらに低侵襲で、体への負担が少ない手術です。
- 日帰り手術が可能: 手術時間が短く、出血も少ないため、日帰り手術が可能です。
デメリット
- 効果が限定的: 軽度のSASにのみ効果が期待できます。
- 再発する可能性: 軟口蓋が再びたるんでしまい、症状が再発することがあります。
費用: 保険適用で約3万円~5万円(3割負担の場合) 入院期間: 日帰りまたは1泊 ※おおよその目安であり、各医療機関により異なります。
鼻中隔矯正術
鼻中隔矯正術は、鼻の真ん中にある壁(鼻中隔)が曲がっているのを矯正する手術です。鼻中隔が曲がっていると、鼻呼吸が阻害され、口呼吸になりやすくなります。口呼吸は、気道を狭くし、SASのリスクを高める要因となります。 メリット
- 鼻呼吸が楽になる: 鼻中隔が矯正されることで、鼻詰まりが解消され、鼻呼吸がしやすくなります。
- SASの予防・改善: 鼻呼吸がしやすくなることで、SASの予防・改善効果も期待できます。
デメリット
- 鼻の形状が変化する可能性: 鼻の形状が変化する可能性があります。手術前に、医師と鼻の形状の変化についてよく相談しておくことが大切です。
- 術後の経過: 鼻詰まりや鼻出血などの症状が一時的に悪化する可能性があります。
費用: 保険適用で約5万円~10万円(3割負担の場合) 入院期間: 約1週間~2週間 ※おおよその目安であり、各医療機関により異なります。
アデノイド切除術
アデノイド切除術は、鼻の奥にあるアデノイド(咽頭扁桃)を切除する手術です。アデノイドは、鼻と喉の境目あたりにあるリンパ組織の塊で、免疫機能に重要な役割を果たしていますが、大きくなりすぎると、鼻呼吸を阻害し、SASの原因となります。 メリット
- 小児のSASに効果: アデノイドが大きいことによるSASは、小児によく見られるため、アデノイド切除術は、小児のSASに効果が高い治療法と言えます。
デメリット
- 術後の経過: 手術後、一時的に鼻詰まりや鼻出血などの症状が出ることがあります。
費用: 保険適用で約3万円~5万円(3割負担の場合) 入院期間: 約1週間 ※おおよその目安であり、各医療機関により異なります。
口蓋扁桃摘出術
口蓋扁桃摘出術は、喉の奥にある口蓋扁桃(扁桃腺)を摘出する手術です。口蓋扁桃も、アデノイドと同様に、免疫機能に重要な役割を果たしていますが、大きくなりすぎると、気道を狭くし、SASの原因となります。 メリット
- 小児のSASに効果: 口蓋扁桃が大きいことによるSASも、小児によく見られるため、口蓋扁桃摘出術も、小児のSASに効果が高い治療法と言えます。
デメリット
- 術後の経過: 手術後、一時的に喉の痛みや発熱などの症状が出ることがあります。
費用: 保険適用で約3万円~5万円(3割負担の場合) 入院期間: 約1週間 ※おおよその目安であり、各医療機関により異なります。 これらの手術は、それぞれにメリットとデメリットがあります。患者さん自身の症状や状態、ライフスタイルなどを考慮した上で、医師とよく相談して手術を受けるかどうかを判断することが大切です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術以外の治療方法
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療は、必ずしも手術が第一選択となるわけではありません。むしろ、まずは手術以外の治療を試みるケースがほとんどです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療は、必ずしも手術が第一選択となるわけではありません。むしろ、まずは手術以外の治療を試みるケースがほとんどです。
なぜなら、SASの症状や重症度は患者さん一人ひとり異なり、軽症であれば手術以外の方法で十分な効果が得られる可能性があるからです。
あなたの症状や生活スタイルに合った治療法を選択することが大切です。
CPAP(シーパップ)療法
CPAP療法は、Continuous Positive Airway Pressure(経鼻的持続陽圧呼吸療法)の略で、睡眠時に鼻に装着したマスクを通して空気を送り込み、気道を広げて呼吸を楽にする治療法です。
イメージとしては、寝ている間に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、空気の力で気道を押し広げてあげることで、いびきや無呼吸を防ぎます。 例えるならば、しぼんでしまった風船に、CPAPという空気入れで空気を送り込み続けることで、風船が膨らんだ状態を保つように、気道が塞がってしまうのを防ぐイメージです。
CPAP療法は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)の第一選択となる治療法とされており、多くの患者さんで高い効果が期待できます。
CPAP療法のメリット
- いびきや無呼吸を効果的に改善できる
- 睡眠の質を向上させることができる
- 日中の眠気や倦怠感を軽減できる
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)に伴う合併症のリスクを低減できる
CPAP療法のデメリット
- マスクの装着感が気になる場合がある
- 鼻詰まりや乾燥を感じることがある
- 旅行などに持っていくのが大変な場合がある
実際に、CPAPを始めたばかりの頃は、マスクの圧迫感や装着することへの抵抗感から、なかなか治療が継続できない患者さんも少なくありません。
しかし、最近では、マスクの種類も豊富になり、顔へのフィット感や圧迫感を軽減したものが増えています。
また、加湿機能付きのものもあり、鼻詰まりや乾燥などの症状も改善されてきています。
マウスピース(口腔内装置)療法
マウスピース療法とは、睡眠時に装着するマウスピースを用いて、下顎(したあご)を少し前に出すことで気道を広げ、いびきや無呼吸を改善する治療法です。
イメージとしては、ボクシングの選手が口に入れるマウスピースに似ており、就寝時に装着することで、下あごを少し前方に固定し気道を確保します。
マウスピース療法は、CPAP療法に比べて、手軽で持ち運びにも便利であるため、近年注目されている治療法です。
マウスピース療法のメリット
- CPAP療法に比べて、装着感が少なく、違和感を感じにくい
- 小型で軽量なため、旅行などに持っていくのも簡単
- 比較的安価である
マウスピース療法のデメリット
- CPAP療法に比べて、効果が低い場合がある
- あごの痛みや違和感を感じることがある
- 歯並びが悪化する可能性がある
マウスピースは、患者さん自身で簡単に着脱できるため、手軽に始められるというメリットがあります。 しかし、顎の位置を固定するため、顎関節症のある方や歯周病が進行している方には適さない場合があります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術治療の費用
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術費用は、手術方法、入院期間、医療機関、そして保険適用範囲によって大きく変動します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術費用は、手術方法、入院期間、医療機関、そして保険適用範囲によって大きく変動します。
例えば、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)を考えてみましょう。これは、のどちんこ周辺の余分な組織を切除し、気道を広げる手術です。健康保険が適用されると、自己負担額は約7~10万円が目安となります。
しかし、これはあくまでも目安です。個室の利用や特殊な医療材料の使用など、状況によって費用は数万円単位で変動します。
さらに、術後の合併症リスクを低減するための精密検査や、入院期間延長、術後の投薬内容によっては、費用はさらに増加する可能性があります。
費用は患者さんにとって非常に重要な要素です。費用の不安を取り除き、安心して手術に臨めるよう、事前に医療機関に確認し、納得のいくまで医師に相談することをおすすめします。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術のリスク
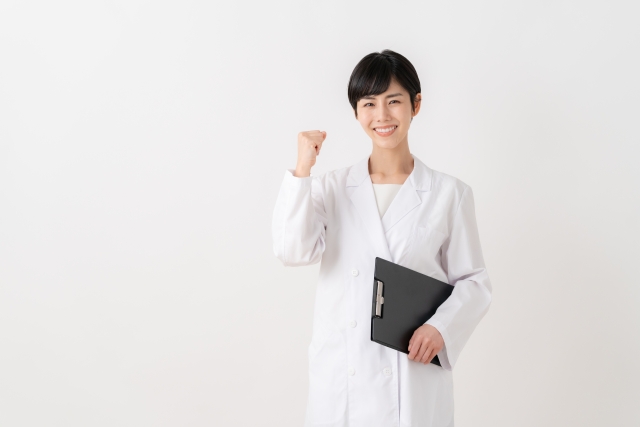 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術は、症状の改善や合併症の予防に繋がる有効な治療法となりえますが、当然ながらリスクも伴います。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術は、症状の改善や合併症の予防に繋がる有効な治療法となりえますが、当然ながらリスクも伴います。
手術を受けるかどうかを判断する際には、メリットだけでなくリスクも十分に理解することが大切です。 ど
んな手術でも、体にとってどうしても負担がかかってしまう部分があります。SASの手術で言えば、鼻やのどを切開したり、組織を切除したりする際に、周囲の組織を傷つけてしまう可能性はゼロではありません。
その結果として、手術後には、以下のようなリスクが生じることがあります。
- 出血:手術中には出血はつきものです。多くの場合は、手術中に適切な処置がとられ、問題となることはありません。しかし、まれに予想以上の出血が起こり、輸血が必要になるケースもあります。
- 感染症:どんな手術にも、感染症のリスクはつきまといます。手術部位が清潔に保たれていなかったり、患者の免疫力が低下していたりすると、細菌が体内に侵入し、感染症を引き起こす可能性が高まります。
- 腫れや痛み:手術後には、手術部位が腫れたり、痛んだりするのは自然な反応です。これは、体が傷を治そうと頑張っているサインでもあります。多くの場合、時間と共に落ち着いていきますが、痛みが強い場合は、痛み止めを使用するなどして、症状を和らげる必要があります。
- 鼻閉:鼻の手術後は、鼻の粘膜が腫れて、鼻詰まりを感じやすくなります。特に、鼻中隔矯正術など、鼻の構造を大きく変える手術を受けた場合には、鼻閉の症状が強く出ることがあります。
- 味覚障害:口蓋垂軟口蓋咽頭形成術などの手術では、口の中の組織を切除するため、一時的に味覚を感じにくくなることがあります。多くの場合、時間と共に回復していきますが、まれに、後遺症として残ってしまうこともあります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の手術の入院期間
 手術の種類や合併症の有無、患者の回復状況によって入院期間は異なりますが、例えば、あごを大きく動かす必要がある上下顎同時前進術のような大規模な手術の場合だと、骨を切って動かすため、体の負担も大きいです。
手術の種類や合併症の有無、患者の回復状況によって入院期間は異なりますが、例えば、あごを大きく動かす必要がある上下顎同時前進術のような大規模な手術の場合だと、骨を切って動かすため、体の負担も大きいです。
そのため、1週間から2週間程度の入院が必要となることが多いです。 一方、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)などの比較的小規模な手術では、入院期間は3日から5日程度で済むケースもあります。
これは、手術自体が体の表面に近い部分に行うものであり、傷口も小さいためです。 入院中は、手術後の出血や腫れ、痛みなどを管理するために、医師や看護師による定期的な診察や処置が行われます。
呼吸状態をモニタリングし、必要に応じて酸素療法なども行われます。 退院後も、定期的な通院が必要となり、医師の指示に従って、日常生活における注意点や、食事、運動などに関する指導を受けていきましょう。
手術の効果を最大限に引き出し、再発を予防するためには、医師の指示をしっかりと守り、適切なアフターケアを受けることが重要です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)のおすすめの治療法は?
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療は、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、最適な方法を組み合わせる必要があります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療は、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、最適な方法を組み合わせる必要があります。
例えば、軽度のSASで、肥満気味で日中眠気が強い40代の男性会社員の方の場合、まずは生活習慣の見直しから始めることが考えられます。会社帰りのジム通いなどで運動を取り入れたり、夕食は腹八分目を心がけたり、寝る前の晩酌をやめてみるなどです。
これらの生活習慣の改善は、体重減量や気道周りの脂肪組織の減少に繋がり、SASの症状改善に効果が期待できます。
一方、中等症〜重症のSASで、高血圧や不整脈などの合併症がある、あるいは生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合は、「CPAP(シーパップ)療法」と呼ばれる治療法が一般的です。
CPAP療法は、鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道を広げて呼吸を楽にする治療法です。これは、例えるならば、夜寝ている間、しぼんでしまった風船に、空気入れで空気を送り込み続けるようなイメージです。
CPAP療法によって、睡眠中の無呼吸や低呼吸を減らし、睡眠の質を向上させることで、日中の眠気や集中力低下などの改善、さらには高血圧などの合併症のリスクを減らす効果も期待できます。
SASの治療は、自分に合った方法を見つけることが大切です。専門医に相談し、検査結果や生活習慣などを考慮しながら、最適な治療法を選びましょう。
睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合はオンライン診療へ
「もしかしたら、睡眠時無呼吸症候群かも…」と感じたら、まずは医療機関に相談してみましょう。
最近は、病院に足を運ばなくても、自宅で気軽に医師の診察を受けられるオンライン診療を提供している医療機関が増えてきました。
オンライン診療では、スマートフォンやパソコンを使って、ビデオ通話などを通して医師に症状や状態を相談することができます。
例えば、「夜中に何度も呼吸が止まっているようだ」「日中、強い眠気に襲われる」「朝起きた時、頭痛がする」といった症状を医師に伝えましょう。
睡眠時無呼吸症候群の診断には、問診だけでなく、検査が必要になることもあります。
オンライン診療では、医師があなたの症状や状態を丁寧に評価し、必要な検査について説明してくれます。 オンライン診療で医師に相談することで、あなたの状態に合った適切な検査や治療方法について、詳しく知ることができます。
睡眠時無呼吸症候群の治療は、早期発見・早期治療がとても大切です。 少しでも気になる症状があれば、一人で悩まず、まずはオンライン診療などを利用して、気軽に医師に相談してみましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療
- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?
- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します
検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?
予防
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介
合併症
症状
原因
傾向
疑い



 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査には、大きく分けて簡易検査と精密検査の2種類があり、検査方法や費用が異なります。ご自身の症状やライフスタイル、そして医師の指示を考慮しながら、最適な検査方法を選びましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査には、大きく分けて簡易検査と精密検査の2種類があり、検査方法や費用が異なります。ご自身の症状やライフスタイル、そして医師の指示を考慮しながら、最適な検査方法を選びましょう。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療費は、まるでオーダーメイドスーツを仕立てるように、患者さん一人ひとりの症状やライフスタイル、そして治療法によって大きく異なります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療費は、まるでオーダーメイドスーツを仕立てるように、患者さん一人ひとりの症状やライフスタイル、そして治療法によって大きく異なります。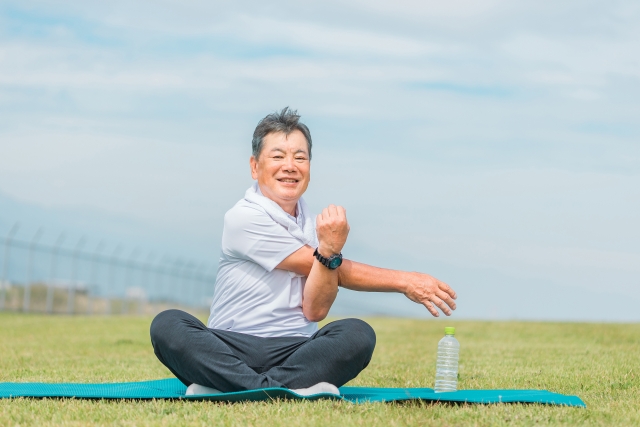
 SASは、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気です。原因は、気道の狭窄。まるで、空気の通り道である喉が、寝ている間に「ふにゃっ」と狭くなってしまうイメージです。
SASは、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気です。原因は、気道の狭窄。まるで、空気の通り道である喉が、寝ている間に「ふにゃっ」と狭くなってしまうイメージです。 「いびきがうるさい」「寝ている時に呼吸が止まっている」なんて言われたことはありませんか?もしかしたら、それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインかもしれません。
「いびきがうるさい」「寝ている時に呼吸が止まっている」なんて言われたことはありませんか?もしかしたら、それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインかもしれません。 ここでは有名なあいうべ体操を取り上げます。 この体操は、舌や口の周りの筋肉を鍛えるトレーニングとして広く知られています。
ここでは有名なあいうべ体操を取り上げます。 この体操は、舌や口の周りの筋肉を鍛えるトレーニングとして広く知られています。 いびきの改善には、舌のトレーニングだけでなく、鼻呼吸のトレーニングも効果的です。普段から口呼吸が多い方は、意識して鼻呼吸をするように心がけましょう。
いびきの改善には、舌のトレーニングだけでなく、鼻呼吸のトレーニングも効果的です。普段から口呼吸が多い方は、意識して鼻呼吸をするように心がけましょう。 睡眠時無呼吸症候群の原因の一つに「肥満」が挙げられます。このため、適度な運動と減量は睡眠時無呼吸症候群に対して有効であると言えます。
睡眠時無呼吸症候群の原因の一つに「肥満」が挙げられます。このため、適度な運動と減量は睡眠時無呼吸症候群に対して有効であると言えます。 「最近、寝ても疲れが取れない」「日中、猛烈な眠気に襲われる」そんな症状はありませんか?もしかしたら、それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインかもしれません。
「最近、寝ても疲れが取れない」「日中、猛烈な眠気に襲われる」そんな症状はありませんか?もしかしたら、それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインかもしれません。
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断された方にとって、どんな寝方が良いのかは気になりますよね。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断された方にとって、どんな寝方が良いのかは気になりますよね。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断された方にとって、横向きで寝ることは効果的です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断された方にとって、横向きで寝ることは効果的です。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の方にとって、横向き寝は効果的な寝方ですが、いくつか注意点があります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の方にとって、横向き寝は効果的な寝方ですが、いくつか注意点があります。 ベッドの角度を調整することも、横向き寝をサポートする方法の一つです。
ベッドの角度を調整することも、横向き寝をサポートする方法の一つです。 横向き寝で効果が出にくいと感じている方には、「うつ伏せ寝」を提案することもあります。
横向き寝で効果が出にくいと感じている方には、「うつ伏せ寝」を提案することもあります。







 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、まるでダムが決壊するように、その原因や重症度によって治る可能性もあれば、付き合っていく必要性も出てくる病気です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、まるでダムが決壊するように、その原因や重症度によって治る可能性もあれば、付き合っていく必要性も出てくる病気です。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたり、「もしかしたら自分も?」と不安に思っている方もいるかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたり、「もしかしたら自分も?」と不安に思っている方もいるかもしれません。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたら、症状の改善や合併症の予防のために、医師の指示に従って適切な治療を受けることが大切です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたら、症状の改善や合併症の予防のために、医師の指示に従って適切な治療を受けることが大切です。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療法は、患者さん一人ひとりの症状の重さや原因、生活習慣によってオーダーメイドで決まります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療法は、患者さん一人ひとりの症状の重さや原因、生活習慣によってオーダーメイドで決まります。 「大きないびきが気になる…」「日中、我慢できないほどの眠気に襲われる…」 そのような症状に悩まされていませんか?
「大きないびきが気になる…」「日中、我慢できないほどの眠気に襲われる…」 そのような症状に悩まされていませんか?
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断には、精密検査が必要です。多くの場合、この精密検査は一晩病院に泊まって行われます。睡眠中の呼吸の状態を詳しく調べるためです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断には、精密検査が必要です。多くの場合、この精密検査は一晩病院に泊まって行われます。睡眠中の呼吸の状態を詳しく調べるためです。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査は、まるで探偵が事件を解決するような、段階的なプロセスを経て行われます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査は、まるで探偵が事件を解決するような、段階的なプロセスを経て行われます。 「自宅でできる簡易検査」は、文字通り自宅で手軽にできる検査です。指に洗濯バサミのような小さな機械を挟んで寝るだけで、睡眠中の呼吸の状態(呼吸が止まっていないか、いびきがうるさくないかなど)を測ることができます。
「自宅でできる簡易検査」は、文字通り自宅で手軽にできる検査です。指に洗濯バサミのような小さな機械を挟んで寝るだけで、睡眠中の呼吸の状態(呼吸が止まっていないか、いびきがうるさくないかなど)を測ることができます。 ここでは検査入院の流れを具体的にイメージしやすいように、病院での1泊2日を例にお話していきます。 まずは病院で入院の手続きを済ませます。
ここでは検査入院の流れを具体的にイメージしやすいように、病院での1泊2日を例にお話していきます。 まずは病院で入院の手続きを済ませます。
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたり、その可能性を指摘されたりすると、一体どの診療科を受診すれば良いのか迷ってしまいますよね。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたり、その可能性を指摘されたりすると、一体どの診療科を受診すれば良いのか迷ってしまいますよね。






 CPAP(シーパップ)用のマスクには、いくつかの種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
CPAP(シーパップ)用のマスクには、いくつかの種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。