
「最近、疲れが取れない」「朝起きてもスッキリしない」と感じていませんか? もしかしたら、それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインかもしれません。
この記事では、睡眠時無呼吸症候群の疑いチェックリストについて詳しく解説します。
ご自身の症状をチェックして、睡眠時無呼吸症候群の可能性について考えてみましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いチェック!自分でできる症状チェックリスト

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まってしまう病気です。
自覚症状が少ないため、気づかないまま放置してしまうケースも多いのですが、実は放っておくと高血圧や心臓病、脳卒中などのリスクを高めてしまう危険な病気です。
ご自身で簡単にできる睡眠時無呼吸症候群の疑いチェックリストをご用意しました。ぜひ、チェックしてみてください。
あなたはいくつ当てはまりますか?
- 大きないびきをかいている。(家族やパートナーから指摘されたことがある場合も当てはまります)
- 睡眠中に呼吸が止まっていると指摘されたことがある。
- 日中に、会議中や運転中に強い眠気に襲われることが多い。
- しっかり寝ても日中眠い、体がだるい、やる気が出ない。
- 高血圧である、もしくは降圧剤を飲んでも血圧が下がりにくい。
- 夜間にトイレに起きることが多い。
- 最近メタボリックシンドロームの傾向を指摘された。
- あごが小さく二重あごもしくはあごのくびれがない。
これらの項目は、睡眠時無呼吸症候群の典型的な症状の一部です。
例えば、大きないびきは気道の狭窄が原因で発生し、睡眠時無呼吸症候群患者さんの多くに見られます。
また、日中の眠気は、睡眠中の無呼吸によって脳が十分に休息できていないために起こります。
これらの項目に多く当てはまる方は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。ご心配な方は、医療機関への受診をおすすめします。
チェックがついたら要注意!睡眠時無呼吸症候群(SAS)の主な症状

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まってしまう病気です。
自覚症状が少ないため、気づかないまま放置してしまうケースも多いのですが、実は放っておくと、高血圧や心臓病、脳卒中などのリスクを高めてしまう危険な病気なのです。
「私は大丈夫!」そう思っている方も、ぜひ一度、ご自身の症状をチェックしてみて下さい。
口やのどの渇き
朝起きたとき、口やのどがカラカラに乾いていることはありませんか?
健康な状態であれば、就寝中に多少のどが渇くことはあっても、朝起きた時に極端に乾燥していると感じることは少ないでしょう。
しかし、睡眠時無呼吸症候群の人は、睡眠中に何度も呼吸が止まってしまうため、口呼吸になりがちです。
その結果、口やのどが乾燥し、朝起きたときに強い渇きを感じることがあります。
例えば、
- 寝る前にコップ一杯の水を飲んでも、朝にはなくなっている
- 口の中がネバネバする
- のどがイガイガする
- 舌がヒリヒリする
このような症状があれば、要注意です。
熟眠感がない
「ぐっすり眠れた!」という感覚がない場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
睡眠は、ただ長時間眠ればいいというわけではありません。睡眠の「質」が重要なのです。
睡眠時無呼吸症候群になると、睡眠中に何度も呼吸が止まってしまうため、深い睡眠が得られにくくなります。
例えば、
- 朝起きても、体が重だるい
- 頭がスッキリしない
- 日中、強い眠気に襲われる
- 何度も目が覚めてしまう
このような症状があれば、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。
居眠り
会議中や運転中など、起きていなければならない場面で、強い眠気に襲われることはありませんか?
健康な状態であれば、たとえ睡眠時間が短かったとしても、会議中や運転中に強い眠気に襲われることは、まずありません。
睡眠時無呼吸症候群の人は、睡眠不足の状態になっているため、日中に強い眠気に襲われることがあります。
例えば、
- 信号待ちで、ついウトウトしてしまう
- テレビを見ながら、寝落ちしてしまう
- 仕事中に、集中力が続かない
- 電車の中で座るとすぐに眠ってしまう
このような経験があれば、要注意です。
慢性的な疲労感
十分な睡眠をとっているはずなのに、常に疲労感を感じている場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
「疲れている」と感じやすい方は、もしかしたら、睡眠の質が低下しているせいで、体や脳がしっかりと休めていないのかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群になると、睡眠の質が低下するため、体や脳がしっかりと休まりません。
例えば、
- 朝から体がだるい
- 常に疲れを感じている
- 何をするにも、やる気が起きない
- 休日も寝てばかりいる
このような症状が続いている場合は、医療機関への受診も検討しましょう。
集中力の低下
仕事や勉強に集中できない、ミスが増えたなど、集中力の低下を感じたら、睡眠時無呼吸症候群の可能性も考えられます。
「あれ?最近、集中力が続かないな…」 「以前は簡単にできた仕事が、最近はミスばかり…」
このような経験はありませんか?
睡眠時無呼吸症候群になると、脳が酸素不足に陥るため、集中力や記憶力、判断力などの認知機能が低下する可能性があります。
例えば、
- 本を読んでも、内容が頭に入ってこない
- 計算ミスが増えた
- 物忘れがひどくなった
- 会話中に、相手の名前が出てこない
と感じたら、注意が必要です。
関連記事
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状をわかりやすく解説!自分でできる症状チェックリスト付き
睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合はオンライン診療へ
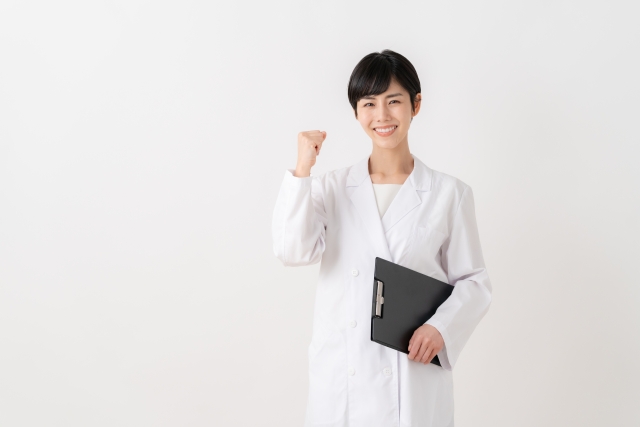
以上のようなチェックリストに当てはまる方は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まってしまい、質の高い睡眠を妨げる病気です。
自覚症状が少ないため、多くの方が気づかないまま放置してしまいがちですが、実は高血圧や心臓病、脳卒中などのリスクを高める危険な病気です。
「でも、仕事が忙しくて病院に行く時間がない…」
そんな方でも、最近はスマホやパソコンを使って自宅で診察を受けられるオンライン診療があります。
オンライン診療であれば、病院に行く時間がない方でも、自分のペースで受診できます。
「もしかしたら、私も睡眠時無呼吸症候群かもしれない…」 そう感じたら、一人で悩まず、まずはオンライン診療で相談してみて下さい。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療
- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?
- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します
検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?
予防
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介
合併症
症状
原因
傾向
疑い
日付: 2024年9月27日 カテゴリ:セルフチェック and tagged SAS, セルフチェック, チェック, チェックリスト, 睡眠時無呼吸症候群

































 「朝起きたら頭が痛い…」「なんだか最近、頭痛が多い気がする…」と感じていませんか?
「朝起きたら頭が痛い…」「なんだか最近、頭痛が多い気がする…」と感じていませんか? 睡眠時無呼吸症候群になると、寝ている間に呼吸が何度も止まり、体が酸素不足の状態になってしまいます。
睡眠時無呼吸症候群になると、寝ている間に呼吸が何度も止まり、体が酸素不足の状態になってしまいます。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、寝ている間に呼吸が止まり、体が酸素不足になってしまう病気です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、寝ている間に呼吸が止まり、体が酸素不足になってしまう病気です。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)によって、夜間に十分な睡眠がとれていないため、日中にさまざまな症状が現れます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)によって、夜間に十分な睡眠がとれていないため、日中にさまざまな症状が現れます。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因で起こる頭痛は、寝ている間に呼吸が何度も止まり、脳が酸素不足になることで起こると考えられています。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因で起こる頭痛は、寝ている間に呼吸が何度も止まり、脳が酸素不足になることで起こると考えられています。
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の患者さんのそばで寝ていると、呼吸が止まってしまい「このまま息をしなくなってしまうのではないか」と不安になるかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の患者さんのそばで寝ていると、呼吸が止まってしまい「このまま息をしなくなってしまうのではないか」と不安になるかもしれません。 健康な人であれば、寝ている間も脳が呼吸をコントロールしているので、呼吸が止まることはありません。しかし、睡眠時無呼吸症候群の患者さんの場合、睡眠中に気道が塞がってしまうことで、一時的に呼吸が止まってしまうのです。
健康な人であれば、寝ている間も脳が呼吸をコントロールしているので、呼吸が止まることはありません。しかし、睡眠時無呼吸症候群の患者さんの場合、睡眠中に気道が塞がってしまうことで、一時的に呼吸が止まってしまうのです。




 「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という病気は、寝ている間に呼吸が止まってしまう病気です。単なる「いびき」と安易に考えてはいけません。
「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という病気は、寝ている間に呼吸が止まってしまう病気です。単なる「いびき」と安易に考えてはいけません。 睡眠時無呼吸症候群はさまざまな理由で死亡につながるリスクが高まることをお伝えしてきました。
睡眠時無呼吸症候群はさまざまな理由で死亡につながるリスクが高まることをお伝えしてきました。 自覚症状が乏しい場合も多い睡眠時無呼吸症候群ですが、実は、適切な治療を受けずに放置すると寿命にも影響する可能性があります。
自覚症状が乏しい場合も多い睡眠時無呼吸症候群ですが、実は、適切な治療を受けずに放置すると寿命にも影響する可能性があります。 「睡眠時無呼吸症候群と診断されました。でも、治療は面倒だし、自覚症状もないので、放っておいても大丈夫ですよね…?」
「睡眠時無呼吸症候群と診断されました。でも、治療は面倒だし、自覚症状もないので、放っておいても大丈夫ですよね…?」 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、決して「ただのいびき」と安易に考えてはいけません。自覚症状が少ないため、自分がその怪物の餌食になっていることに気づかないまま、健康を蝕まれ、寿命を縮めてしまうことさえあるのです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、決して「ただのいびき」と安易に考えてはいけません。自覚症状が少ないため、自分がその怪物の餌食になっていることに気づかないまま、健康を蝕まれ、寿命を縮めてしまうことさえあるのです。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたり、心配な症状がある方は、まずできることから取り組んでみましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたり、心配な症状がある方は、まずできることから取り組んでみましょう。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたら、生活習慣の改善と並行して、医療機器やグッズを取り入れてみましょう。 ここでは、代表的な対策グッズを3つご紹介します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたら、生活習慣の改善と並行して、医療機器やグッズを取り入れてみましょう。 ここでは、代表的な対策グッズを3つご紹介します。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されると、不安な気持ちになる方もいるかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されると、不安な気持ちになる方もいるかもしれません。