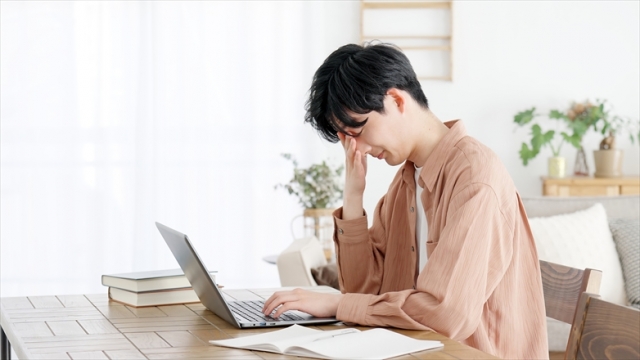「睡眠時無呼吸症候群(SAS)=太った中年男性の病気」というイメージが強いかもしれません。
しかし、実は女性も睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症することがあります[1]。
特に閉経前後のホルモン変化や体型変化が重なり、50代以降では男性に匹敵する有病率になるとの報告もあります[2]。
もし「いびきをかくなんて男性だけでしょ」「私はただ疲れているだけ」と思って放置していると、重大なリスクにつながる可能性があります。
本記事では、女性に多い睡眠時無呼吸症候群(SAS)の特徴や見逃されやすい理由、セルフチェック方法から治療・受診の流れまで、医学的エビデンスを踏まえてわかりやすく解説します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症割合はどれくらい?

世界的な有病率
世界的には成人人口の**約9〜38%**が閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)の診断基準を満たすと推定されています[3]。
ただし、症状の程度(軽症〜重症)によって幅があり、実際に受診・治療を受けている人はそのうちの一部です。
日本人の場合
日本人成人のOSAS有病率は3〜9%程度とされますが[4]、BMIが欧米人より低くても発症しやすい傾向があると報告されています[5]。
これは顎の骨格や上気道の狭さなどアジア人特有の形態が影響していると考えられています[5]。
女性特有の状況
「女性のOSAS有病率は男性の半分程度」と言われていますが[1]、これは閉経前の女性を含むトータルな数字です。
閉経後はホルモン分泌の変化に伴って有病率が大きく上昇し、同年代男性と同等に近づくというデータがあります[2]。
つまり、更年期以降の女性は注意が必要です。
関連記事
痩せてるのに睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性あり?原因・リスク・治療法を徹底解説!
「睡眠時無呼吸症候群(SAS)はどんな人がなるの?」傾向と特徴を徹底解説
年代別・性別の割合と特徴

- 若年層(20〜30代)
- 一般に男性がやや多い傾向がありますが、女性でも肥満度や顎の形態によっては発症します[6]。
- 女性は症状が軽度だと「ただの疲れ」や「ストレス」と見なされがちで、診断が遅れることも。
- 中年期(30〜50代)
- 男性の有病率が上昇する時期。飲酒習慣や体重増加、喫煙などが重なると睡眠時無呼吸症候群(SAS)リスクがさらに高くなります[7]。
- 女性は閉経前後を境にリスクが上昇。特に更年期障害と症状が紛らわしく、見逃されやすいと言われています[2]。
- 高齢期(60代以上)
- 男性・女性ともに睡眠時無呼吸症候群(SAS)の有病率が高い。筋力や組織の弛緩によって気道が狭くなりやすいことが要因の一つ[8]。
- 女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)の保護作用が低下し、男女差が縮まるのが特徴です[2]。
さらに、女性は「不眠」「朝の頭痛」「抑うつ感」などの症状が出やすく、いびきや無呼吸を自覚しにくい場合があります[9]。
そのため、まったく別の病気や単なるストレスとして見逃してしまうケースが少なくありません。
関連記事
高齢者の睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?症状・原因・治療法を徹底解説!
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の芸能人を紹介!実は治療を受けてる人はたくさんいた!
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群(SAS)を放置するとどうなる?

心血管系疾患のリスク
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠中に何度も呼吸が止まり、血中酸素が低下するため、交感神経が常に刺激され、高血圧や心不全、心筋梗塞、脳卒中などのリスクが高まります[10]。
認知機能の低下
慢性的な低酸素状態と睡眠の質の低下が、認知症や軽度認知障害のリスク上昇に関与すると報告されています[11]。
特に高齢女性は、アルツハイマー病をはじめとする認知症の発症リスクが男性より高い傾向があるため、見過ごせない問題です[12]。
日中の眠気・生活の質の低下
夜間に熟睡できず、何度も無呼吸や低呼吸で目が覚めるため、慢性的な疲労感や日中の強い眠気が生じます[13]。
- 交通事故や産業事故のリスク上昇
- 仕事や家事への集中力低下
- イライラ感や抑うつ傾向
こうした生活の質(QOL)の低下が長期にわたって続くと、心身への負担がさらに大きくなります。
関連記事
睡眠時無呼吸症候群(SAS)が重症化したときの症状と日常生活への影響
自分は大丈夫?セルフチェックと検査方法

セルフチェック:当てはまりませんか?
- 大きないびきを指摘された、あるいは自覚している[2]
- 就寝中に呼吸が止まっていると家族やパートナーに言われた
- 朝起きたときに頭痛や口の渇きを感じる
- 日中に強い眠気があり、仕事や運転に支障をきたす[13]
- 夜間頻尿で何度も目が覚める
- 眠っていても疲れが取れにくく、常にだるさが残る
- ストレスや更年期障害だと思い込んでいるが、実は原因不明の倦怠感がある
上記のうち複数が当てはまる場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。
「女性はいびきなんてかかない」と思い込まず、いったん専門医に相談すると安心です。
検査方法
- 簡易型睡眠ポリグラフ検査(簡易PSG)
自宅で装置を装着し、呼吸状態や酸素飽和度をモニタリングします。手軽に始められ、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性を判定しやすい方法です[14]。 - 終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)
病院やクリニックに一泊し、脳波や呼吸・酸素飽和度などを同時に詳しく測定します。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の確定診断に用いられます[14]。
女性の場合、更年期障害や他の睡眠障害と紛らわしい症状があるため、専門医が総合的に判断することが大切です。
最近はオンライン診療を活用して、初診から検査キットの郵送まで完結できるクリニックも増えています。
関連記事
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある場合はオンライン診療へ

もし睡眠時無呼吸症候群(SAS)を疑う症状があるなら、まずは専門医への相談が近道です。
仕事や家事などで忙しい方でも、オンライン診療なら自宅から受診でき、検査キットも自宅へ郵送されます[15]。
遠方や交通手段がない場合でもスムーズに検査を受けられるのがメリットです。
森下駅前クリニックでは、SASの診察・検査に対応したオンライン診療を行っています。
自宅からスマートフォンやパソコンで専門医に相談でき、必要に応じて簡易睡眠検査機器を宅配で受け取って自宅で測定が可能です。
24時間予約を受け付けているため、隙間時間で受診しやすいメリットがあります。
SASは適切に治療すれば、眠気が改善し、事故や合併症のリスクを大幅に減らすことができる病気です。
睡眠時無呼吸症候群かな?と思ったら、まずはお気軽に森下駅前クリニックのオンライン診療をご利用ください。
私たち専門医が、一人ひとりに合った最適な検査・治療プランをご提案し、快適な睡眠と健康な生活を取り戻すお手伝いをいたします。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療
- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?
- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します
検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?
予防
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介
合併症
症状
原因
傾向
疑い
参考文献(References)
- Bixler EO, et al. Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Women: Effects of Gender. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(3 Pt 1):608-613.
- Dancey DR, et al. Impact of menopause on the prevalence and severity of sleep apnea. Chest. 2001;120(1):151-155.
- Benjafield AV, et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med. 2019;7(8):687-698.
- Nakayama-Ashida Y, et al. Sleep-disordered breathing in the usual lifestyle setting as detected with home monitoring in a population of working men in Japan. Sleep. 2008;31(3):419-425.
- Li KK, et al. Obstructive sleep apnea syndrome: a comparison between Far-East Asian and white men. Laryngoscope. 2000;110(10 Pt 1):1689-93.
- Young T, et al. The Occurrence of Sleep-Disordered Breathing among Middle-Aged Adults. N Engl J Med. 1993;328(17):1230-5.
- Romero-Corral A, et al. Interactions between obesity and obstructive sleep apnea: implications for treatment. Chest. 2010;137(3):711-9.
- Ancoli-Israel S, et al. Sleep-disordered breathing in community-dwelling elderly. Sleep. 1991;14(6):486-95.
- Saaresranta T, Polo O. Hormones and breathing. Chest. 2002;122(6):2165-82.
- Peppard PE, et al. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med. 2000;342(19):1378-84.
- Yaffe K, et al. Sleep-disordered breathing, hypoxia, and risk of mild cognitive impairment and dementia in older women. JAMA. 2011;306(6):613-9.
- Vina J, Lloret A. Why women have more Alzheimer’s disease than men: gender and mitochondrial toxicity of amyloid-β peptide. J Alzheimers Dis. 2010;20 Suppl 2:S527-33.
- Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth Sleepiness Scale. Sleep. 1991;14(6):540-5.
- Kapur VK, et al. Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult Obstructive Sleep Apnea: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med. 2017;13(3):479-504.
- Marin JM, et al. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet. 2005;365(9464):1046-53.
※本記事は医学的知見に基づく情報提供を目的としており、個別の症状や治療法を示すものではありません。気になる症状がある場合は、必ず医師にご相談ください。