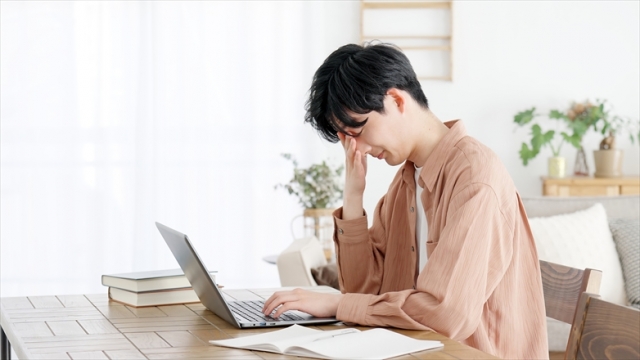睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、眠っている間に繰り返し呼吸が止まる(無呼吸)または浅くなる(低呼吸)病態です。
成人では主に閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)といい、就寝中に咽頭の空気の通り道が狭くなり閉塞することで発生します。
無呼吸・低呼吸により血中の酸素が低下するとともに、脳が頻繁に覚醒(マイクロ覚醒)して睡眠が途切れるため、睡眠の質が著しく低下します。
その結果、十分な睡眠時間をとっていても熟睡感が得られず、日中に強い眠気を感じてしまいます。
実際、SAS患者の約25〜50%に日中の過度の眠気(過眠症状)がみられるとの報告があります【1】。
こうした日中の眠気は、SASを治療することで改善できることが多数のランダム化比較試験(RCT)により確認されています【2】。
例えば、持続陽圧呼吸(CPAP)療法を3ヶ月間行った群では、眠気の指標であるエプワース眠気尺度(ESS)が平均で約3ポイント改善したとのメタ分析結果があります【2】。
これは裏を返せば、SASが日中の眠気の大きな原因となっていることを示すエビデンスです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
放置すると危険!眠気によるリスクとは?

SASによる睡眠の質低下と日中の眠気は、放置すると様々なリスクを招きます。まず仕事のパフォーマンス低下です。
強い眠気により集中力や判断力が落ち、仕事や勉強の能率が著しく低下します。ミスが増えたり判断を誤ったりすることで、生産性の低下だけでなく重大な事故につながる可能性もあります。
また、居眠り運転による交通事故のリスクも無視できません。無治療のSAS患者では交通事故を起こす確率が健常者の約2〜4倍に高まるとのメタ分析報告があり【3】、日中の過度の眠気が重大な事故要因となっています。
さらに適切な治療を受ければ、この事故リスクは大幅に低減または正常化するとされており【4】、SASを放置しないことの重要性が分かります。
加えて、SASを放置すると生活習慣病や心血管疾患のリスクも高まります。
SASでは睡眠中の低酸素状態や交感神経の過剰な活性化が繰り返されるため、高血圧、糖尿病、心疾患(冠動脈疾患や不整脈)、脳卒中などのリスク因子になります【1】。
特に中等度〜重度のSASでは高血圧の合併が多く、夜間に血圧が下がりにくい傾向があります。
実際、CPAP療法による治療によって収縮期・拡張期血圧がわずかではありますが有意に低下することが複数のRCTのメタ分析で示されており【4】、これはSASが高血圧を悪化させている一因であることを示唆しています。
同様に、SAS患者では心疾患や脳卒中の発症率が高いことが報告されています【1】。
このように、SASによる日中の眠気を放置すると、仕事中や運転中の事故リスクだけでなく、長期的な健康リスクにもつながるため注意が必要です。
自分でできる睡眠時無呼吸症候群(SAS)のセルフチェックと簡易検査

「自分もSASかもしれない」と思ったら、まずはセルフチェックを行ってみましょう。
以下のようなポイントに心当たりはないでしょうか?
- 大きないびきを指摘されたことがある(特に断続的ないびきや途切れるいびき)。
- 睡眠中の無呼吸を家族に指摘されたことがある(呼吸が止まっている、息苦しそうにしている)。
- 日中に強い眠気に襲われる(会議中や運転中についウトウトしてしまう)。
- 朝起きたときに頭痛や喉の渇きがある。
- 肥満気味である(BMIが高い)。
- 夜間に何度もトイレに起きる。
- 寝汗をかいたり、睡眠中に息苦しくて目が覚めることがある。
上記に複数当てはまる場合、SASの可能性があります。
特にいびきはSASの重要なサインです。大きないびきを常習的にかいている場合、その裏で無呼吸発作が起きている可能性があります。
また、自覚的な眠気の程度を測る方法として「エプワース眠気尺度(ESS)」という簡便な問診票があります。
8つの状況下で居眠りしてしまう可能性を0〜3点で評価し合計点を出すもので、一般に10点以上は日中の過度の眠気が疑われます。
ESSはインターネット上でも自己評価できますので、一度試してみると良いでしょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
最近では、スマホアプリやウェアラブルデバイスを利用して自宅で睡眠時無呼吸の兆候をモニターする方法も登場しています。
スマートフォンのマイクで睡眠中のいびきのパターンを録音・解析したり、腕時計型のウェアラブル端末で心拍数や血中酸素飽和度を測定したりすることで、SASの疑いをスクリーニングするアプリがあります。
しかし、現時点ではこれら市販アプリの精度は必ずしも高くありません。2022年のシステマティックレビューによれば、市販の睡眠時無呼吸検出アプリは医療標準の検査と比べて感度・特異度がやや低く、科学的な検証が不十分と結論づけられています【5】。
したがって、スマホアプリ等で「無呼吸の疑いあり」と出ても過信は禁物ですが、受診のきっかけにするには有用でしょう。
医療機関では、まず簡易検査(在宅睡眠時無呼吸検査)を検討します。
簡易検査では、自宅で携帯式の簡易測定装置を一晩装着して、主に呼吸の気流や胸部の動き、血中酸素の低下などを記録します。
簡易検査は測定項目が限定的なものの、中等度以上のSASの診断には有用であり、従来の入院検査と比較しても診断精度は十分とされています【4】。
実際、最近の研究では自宅での簡易検査とオンライン診療を組み合わせたアプローチでも、従来型の検査に劣らない有効性が示されています【4】。
まずは簡易検査でSASの有無をスクリーニングし、必要に応じて精密検査や治療につなげることができます。
簡易検査のみで診断困難な場合は終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)が必要です。PSGは病院で一泊して行う精密検査で、脳波や呼吸気流、酸素飽和度などを測定し、一晩の無呼吸低呼吸指数(AHI)を算出します。
しかし、「いきなり病院で一泊検査はハードルが高い…」という方も多いでしょう。現在は、検査機器の普及もあり自宅でもPSG検査が可能となってきています。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)による眠気の改善方法

SASと診断された場合, その治療によって日中の眠気は大きく改善が期待できます。
主な治療法としてはCPAP(シーパップ)治療、マウスピース治療、外科的手術治療、そして生活習慣の改善があります。
患者さんそれぞれの症状の程度や原因に応じて適切な治療法を選択します。
◆ CPAP(持続陽圧呼吸療法)
中等度〜重度のSASに対する第一選択の治療法です。
就寝時に鼻(あるいは鼻口)マスクを装着し、ホースを通じて小型機械から気道に空気を送り込みます。
気道に空気圧をかけて喉の通り道を広げた状態に保つことで、睡眠中の無呼吸発作を防止します。
CPAPを用いると一晩で無呼吸・低呼吸がほぼゼロにまで減少し、睡眠中の酸素低下や覚醒反応も劇的に改善します。
日中の眠気も多くの患者で著明に軽減し、RCTのメタ分析でもCPAP使用群でESS(眠気スコア)が有意に低下しています【2】。
特に重症のSASで日中の眠気が強かった患者ほどCPAPの効果が大きく、眠気スコアが5ポイント以上改善したとの報告もあります【2】。
CPAP治療により得られる効果は眠気の改善に留まりません。無呼吸によるいびきの消失、夜間頻尿の改善、起床時の頭痛や倦怠感の解消など睡眠の質全般の向上が得られます。
それに伴い、仕事中の集中力や活力が増し、生活の質(QOL)が改善することも確認されています【4】。
さらに、CPAPの長期使用により高血圧が改善したり、心血管イベントリスクが低減する可能性も示唆されています【4】。
特にCPAPを適切に使用することで、居眠り運転による事故リスクが正常な人と変わらないレベルまで低下したとの報告もあります【4】。
このように、CPAP治療はSASによる様々な悪影響を総合的に改善できるエビデンスの確立した治療法です。
CPAP治療で重要なのは「毎晩しっかり使い続ける」ことです。
効果を得るには少なくとも1晩4時間以上、できれば就寝中ずっと装着する必要があります。CPAPを正しく使用した方では脳波上の睡眠パターンも正常化し日中の眠気が改善しますが、使用を中断すると再び無呼吸が生じ眠気もぶり返します。
そのため、根本的な治療というよりは「睡眠時に機械で補助し続ける対症療法」と位置づけられますが心拍数の安定、低酸素状態の回避など他に変えられない効果もあります。
また近年はCPAP装置の小型化・静音化が進み、自宅で無理なく使えるよう工夫されています。
CPAPマスクのフィッティングや加湿器の利用などで快適性も向上しており、多くの患者さんが継続使用による眠気改善効果を実感しています。
◆ 減量など生活習慣の改善
体重管理はSAS治療の基本です。
肥満はSASの最大の危険因子であり、首回りや舌、咽頭周囲の脂肪沈着が気道を狭くして無呼吸を悪化させます。
逆に言えば、肥満傾向にあるSAS患者では減量するだけで無呼吸が大幅に改善する可能性があります。
実際、肥満の2型糖尿病患者を対象とした大規模RCT(Sleep AHEAD研究)では、平均10kgの減量により無呼吸・低呼吸指数(AHI)が約30%改善し、重症のSAS患者の割合が半減したと報告されています【6】。
また、この研究では1年後に約3倍もの患者でSASが寛解(AHI正常化)したという画期的な結果も出ています【6】。
減量により気道周囲の脂肪が減少し喉の構造が広がることで、睡眠中の無呼吸発生が減少すると考えられます。
したがって、BMIが高めのSAS患者には食事・運動療法による減量指導が不可欠です。5〜10%程度の体重減少でもSASの重症度は有意に改善するとの報告があり【6】、眠気やいびきも軽減することが期待できます。
加えて、禁酒・節酒も重要です。
アルコールには筋肉を弛緩させる作用があるため、就寝前の飲酒は咽頭の閉塞を助長し無呼吸を悪化させます。
睡眠薬や抗不安薬などの鎮静剤も同様に気道を狭める可能性があるため、医師と相談が必要です。
そのほか、仰向けで眠ると重力で舌根が喉に落ち込みやすいため、横向き寝(側臥位)を心がける、寝室内の環境整備や十分な睡眠時間の確保など睡眠衛生を良くすることも症状改善に役立ちます。
◆ マウスピース(口腔内装置)治療
軽症〜中等度のSASや、下顎が小さい(後退している)タイプのSASに対して有効なのが、歯科装着型のマウスピース治療です。
正式には下顎前方置換装置(Mandibular Advancement Device;MAD)と呼ばれ、就寝時に装着することで下あご全体を前方に押し出し固定します。
下あごと一緒に舌や舌根も前方に引っ張られるため、結果的に喉の奥の気道が広がり無呼吸が起こりにくくなる仕組みです。
マウスピースは専用の歯科で患者ごとに型取りして作製します。効果としては、いびきの音量低下や無呼吸発作の減少が期待でき、日中の眠気も改善する患者が多くいます【7】。
実際、複数のRCTを対象としたメタ分析では、マウスピース治療は無治療に比べてAHI(無呼吸指数)とESSを有意に改善し、日中の眠気やQOLの改善効果はCPAP治療に匹敵するとの報告があります【7】。
一方で、無呼吸そのものを減らす効果(AHIの低下幅)はCPAPに比べるとやや劣る傾向があり、とくに重症のSASではCPAPほどの十分な効果が得られない場合もあります【7】。
そのため、マウスピース治療は軽症〜中等度のSASやCPAPがどうしても継続困難なケースで検討されることが多いです。
マウスピースは小型で携帯しやすく、旅行や出張の多い方にも使いやすいメリットがあります。
ただし適切な治療効果を得るには歯科での細かな調整や定期的なメンテナンスが必要です。
また、顎関節への負担や歯の動揺といった副作用が生じる場合もあるため、専門医の指導のもと使用しましょう。
◆ 手術による治療
SASの原因がアデノイド肥大や扁桃肥大、軟口蓋(のどちんこ周辺)の形状など解剖学的な要因にある場合、外科的手術による治療が考慮されます。
代表的な手術は口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)で、軟口蓋やのどちんこ(口蓋垂)周囲の余分な組織を切除・縫縮して気道を広げます。
その他、下顎骨や上顎骨を前方へ移動固定する顎骨手術(顎顔面手術)や、舌の一部を切除する手術など、患者さんの解剖に応じて施術が選択されます。
手術は体への侵襲がありますが、解剖学的適応のある患者では根治的効果が期待できます。
例えば、比較的若年で扁桃肥大を伴う患者にUPPPを施行したランダム化比較試験では、手術6ヶ月後に無呼吸指数(AHI)が手術なし群に比べ約60%改善し、日中の眠気や主観的な睡眠の質も有意に向上したと報告されています【8】。
さらに術後2年経過しても効果が持続し、患者のQOLが安定的に改善していることが確認されています【8】。
ただし、SASに対する手術の効果は患者の状態によってばらつきが大きく、必ずしも全員に劇的な改善が得られるわけではありません。
肥満を伴うSASではまず減量やCPAPが優先され、手術は他の治療が無効なケースや解剖学的に手術適応が明確なケースに限られます。
また手術後に時間経過とともに効果が減弱したり、新たな狭窄が生じたりする可能性もあります【8】。
手術治療を検討する際は、睡眠医療に詳しい耳鼻咽喉科や歯科口腔外科と連携し、慎重に適応判断を行うことが重要です。
このように、SASによる日中の眠気は適切な治療によって大きく改善できます。
特にCPAP治療はエビデンスが豊富であり、眠気だけでなく様々な合併症リスクの低減につながることが示されています【4】。
マウスピースや手術、生活習慣の是正なども患者ごとに組み合わせて実施することで、日中の眠気から解放され快活な日常生活を取り戻すことが可能です。
睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合はオンライン診療へ

「もしかしてSASかも?」と思ったら、できるだけ早めに専門医に相談しましょう。
近年はオンライン診療(遠隔医療)の普及により、自宅にいながら専門医の診察を受けることも可能になっています。
日中忙しくて病院に行けない方や、遠方にお住まいで専門クリニックが近くに無い方でも、スマホやパソコンを通じて睡眠医療の専門医にアクセスできます。
オンライン診療を活用すれば、まずは問診によるスクリーニングや簡易検査キットの手配をしてもらい、自宅で検査を行った結果に基づいて診断を受けることができます。
その後、治療が必要と判断されればCPAP装置の手配や指導もオンラインで受けることが可能です。
実際、在宅でのCPAP導入と遠隔フォローアップでも対面診療と同等の患者転帰が得られることが示されており【4】、オンライン診療を上手に活用すれば通院負担を減らしつつ効果的な治療を受けられます。
また、CPAP装置には通信機能が備わっており、装着時間や無呼吸の改善状況が自動でクラウドに記録されます。
主治医はそのデータを遠隔で確認できるため、オンライン上で治療のモニタリングや微調整を行うことも可能です【4】。
このように、オンライン診療はSASの早期診断・治療において強力なサポート手段となっています。
SASは放置すると先述のように日中の著しい眠気による事故リスクや、長期的な健康リスクを伴う疾患です。
しかし、適切に対処すれば決して怖がる必要はありません。オンライン診療もうまく活用しながら早期に専門医に相談し、必要な検査と治療を受けることで、質の高い睡眠と安全な日常生活を取り戻すことができます。
睡眠時無呼吸症候群かな?と思ったら、まずはお気軽に森下駅前クリニックのオンライン診療をご利用ください。
私たち専門医が、一人ひとりに合った最適な検査・治療プランをご提案し、快適な睡眠と健康な生活を取り戻すお手伝いをいたします。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで
保険適用
睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療
- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法
- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?
- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します
検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!
- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?
予防
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介
合併症
症状
原因
傾向
疑い
参考文献
[1] Lévy P, Kohler M, McNicholas WT, et al. Obstructive sleep apnoea syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2015;1:15015.
[2] Patel SR, White DP, Malhotra A, et al. Continuous positive airway pressure therapy for treating sleepiness in a diverse population with obstructive sleep apnea: results of a meta-analysis. Arch Intern Med. 2003;163(5):565-571.
[3] Tregear S, Reston J, Schoelles K, Phillips B. Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: a systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med. 2009;5(6):573-581.
[4] Patil SP, Ayappa I, Caples SM, et al. Treatment of adult obstructive sleep apnea with positive airway pressure: an American Academy of Sleep Medicine systematic review, meta-analysis, and GRADE assessment. J Clin Sleep Med. 2019;15(2):301-334.
[5] Baptista PM, Martin F, Ross H, et al. A systematic review of smartphone applications and devices for obstructive sleep apnea. Braz J Otorhinolaryngol. 2022;88(Suppl 5):S138-S147.
[6] Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH, et al. A randomized study on the effect of weight loss on obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes: the Sleep AHEAD study. Arch Intern Med. 2009;169(17):1619-1626.
[7] Sharples LD, Clutterbuck-James AL, Glover MJ, et al. Meta-analysis of randomised controlled trials of oral mandibular advancement devices and continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea. Sleep Med Rev. 2016;27:108-124.
[8] Sundman J, Friberg D, Browaldh N, et al. Sleep quality after modified uvulopalatopharyngoplasty: results from the SKUP3 randomized controlled trial. Sleep. 2018;41(1):zsx180.